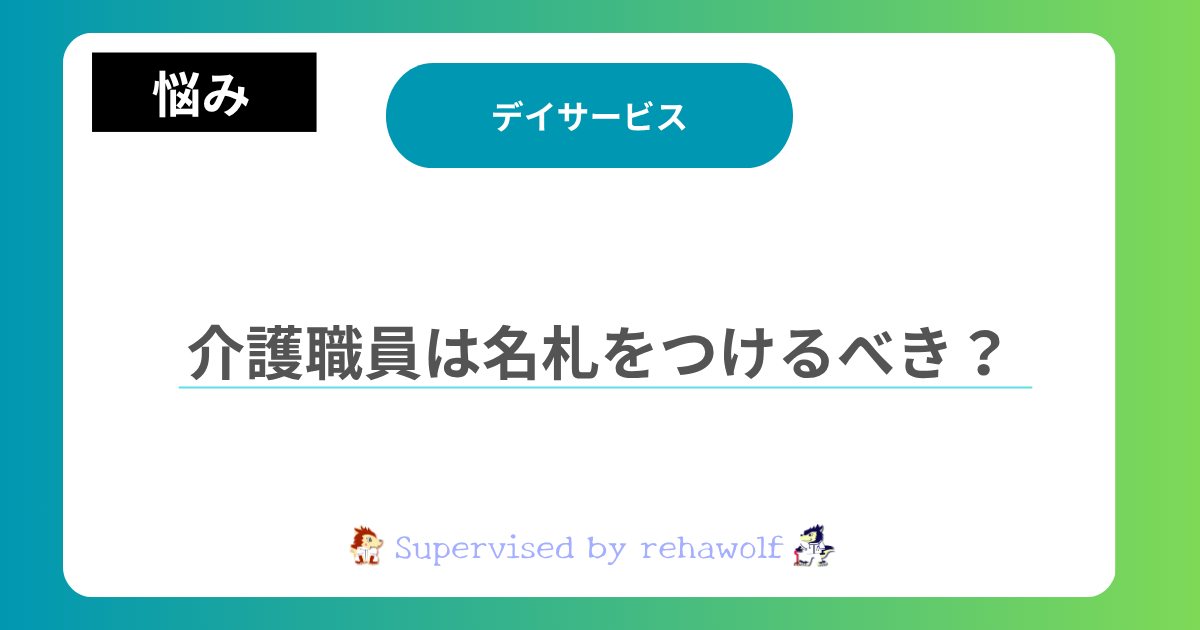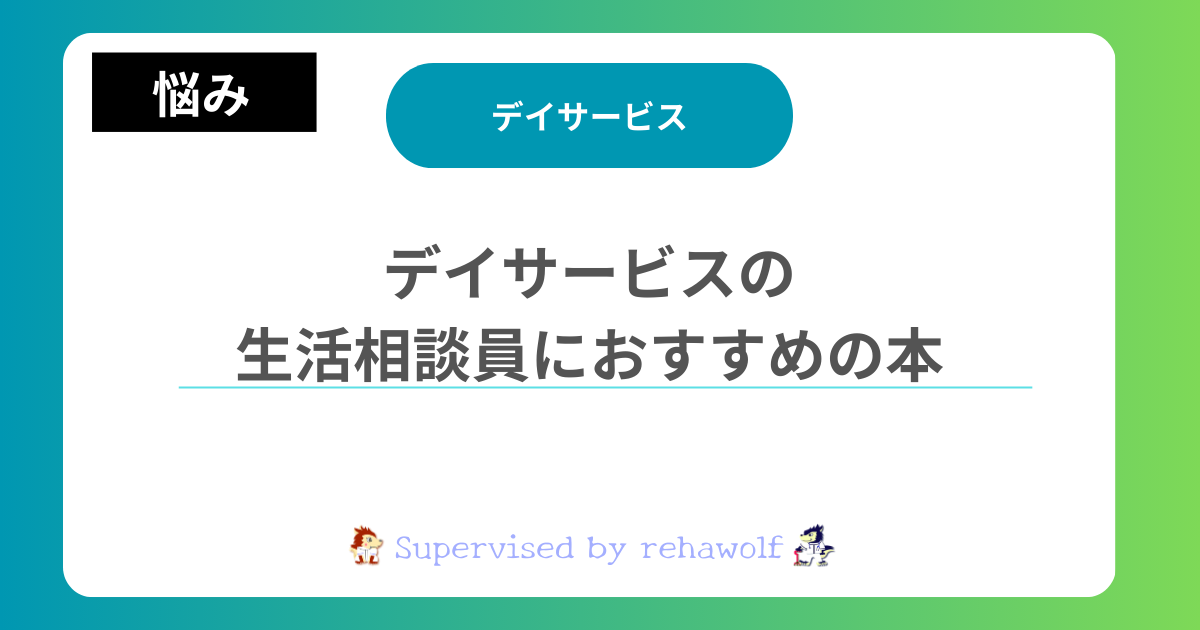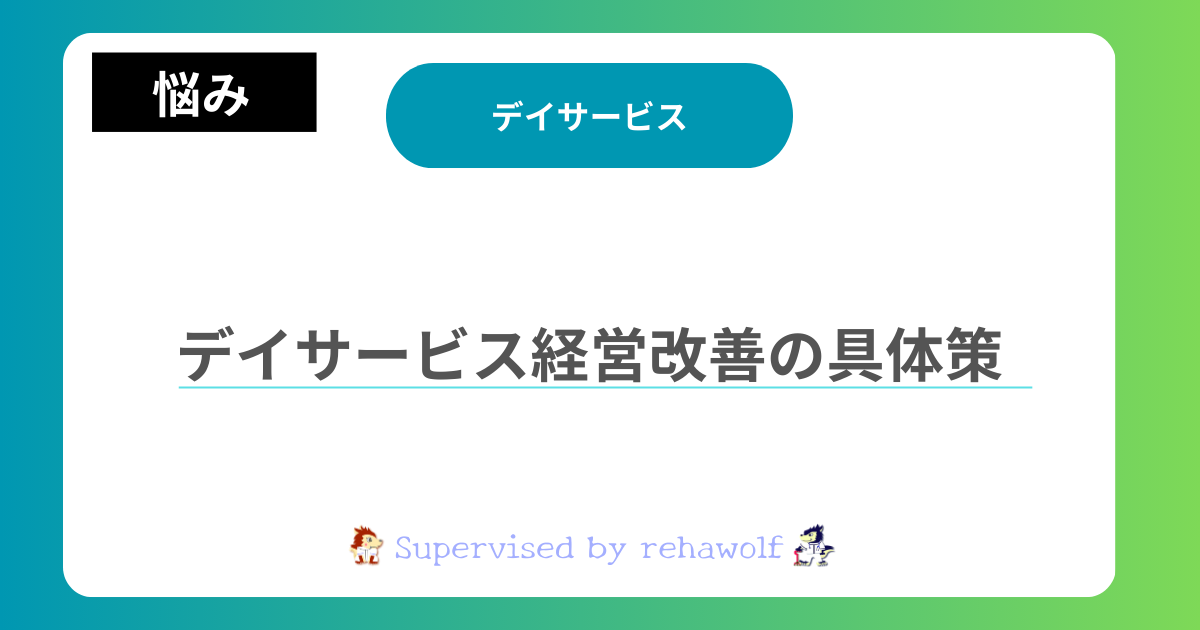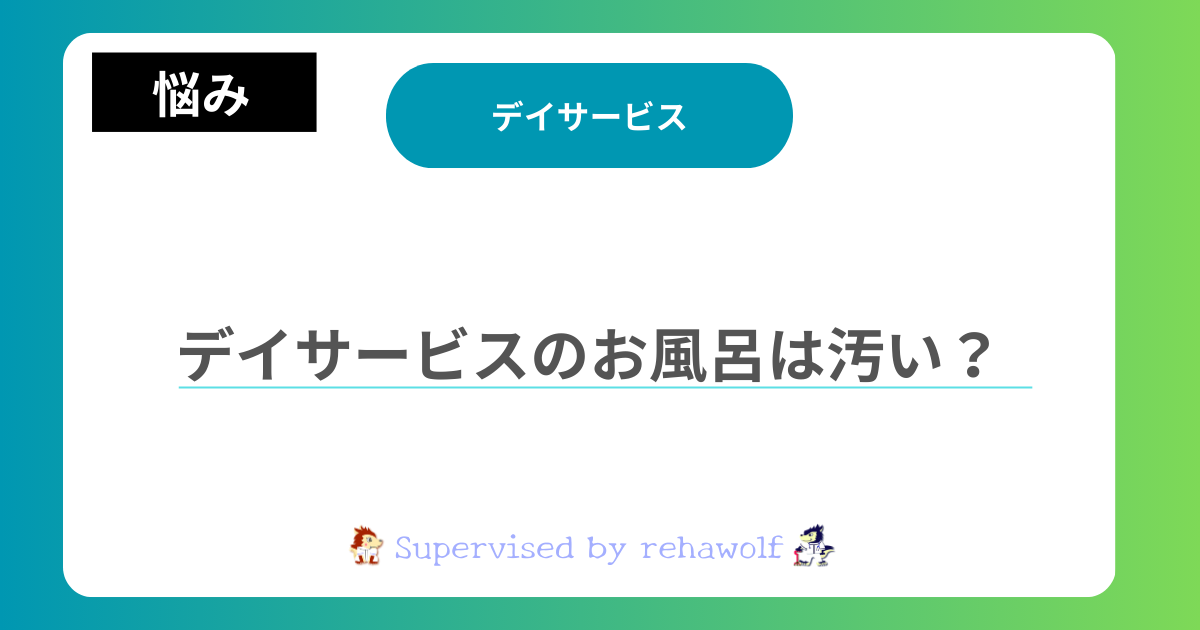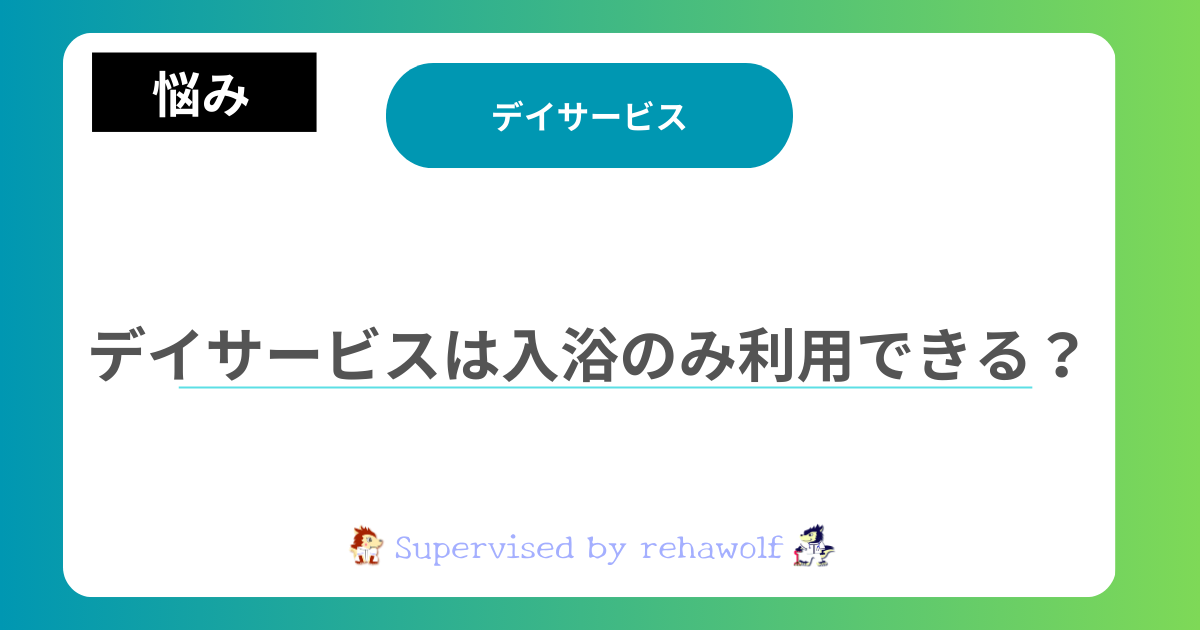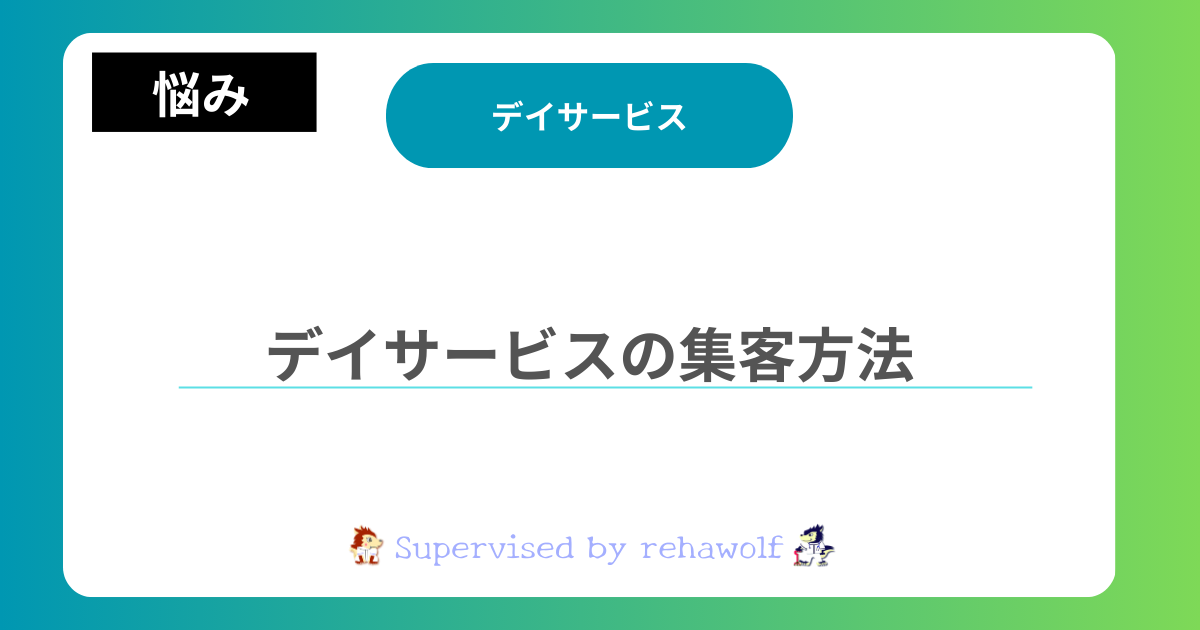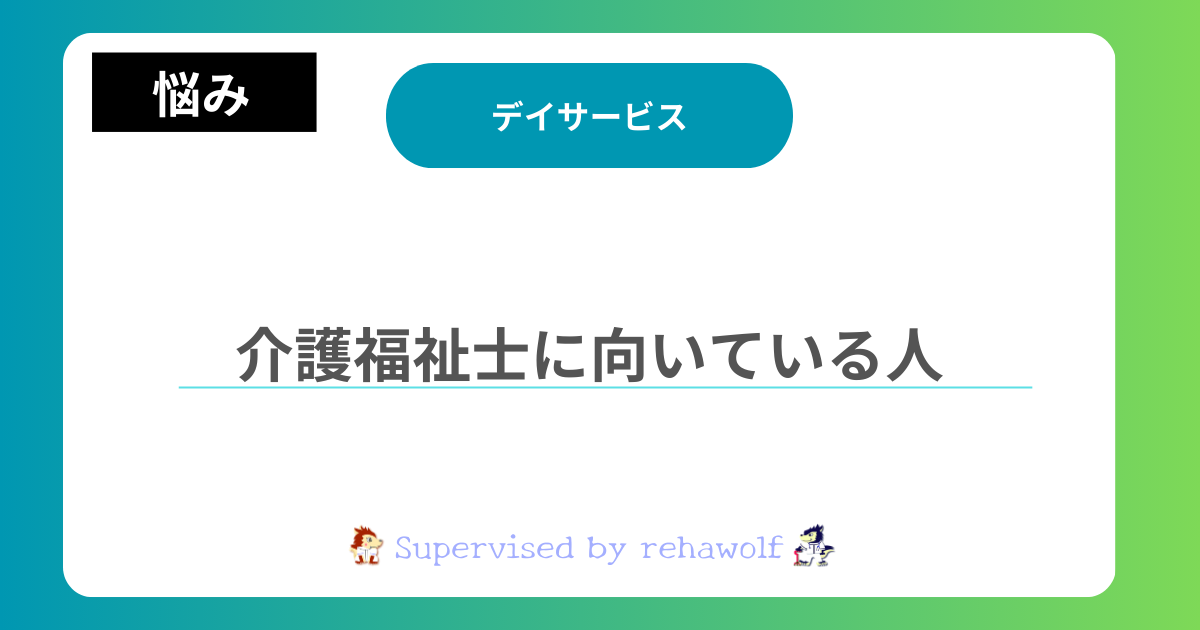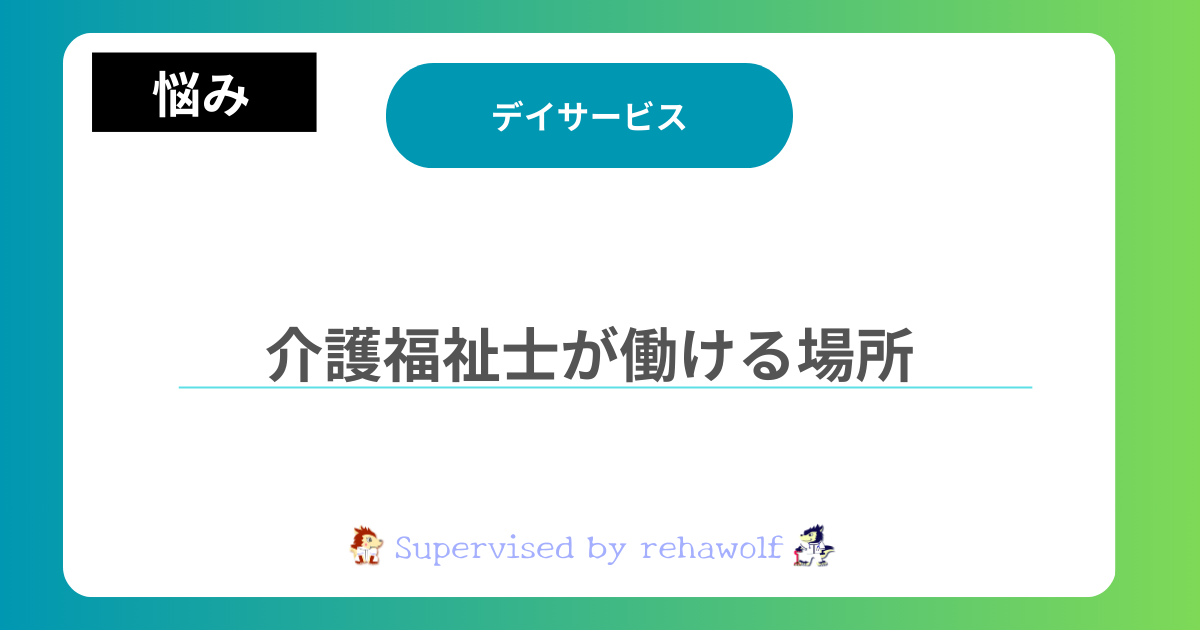【最新】通所介護(デイサービス)のおすすめの本を紹介
機能訓練とリハビリテーションの違いとは?デイサービスで行われる支援を解説
当ページのリンクには広告が含まれています。
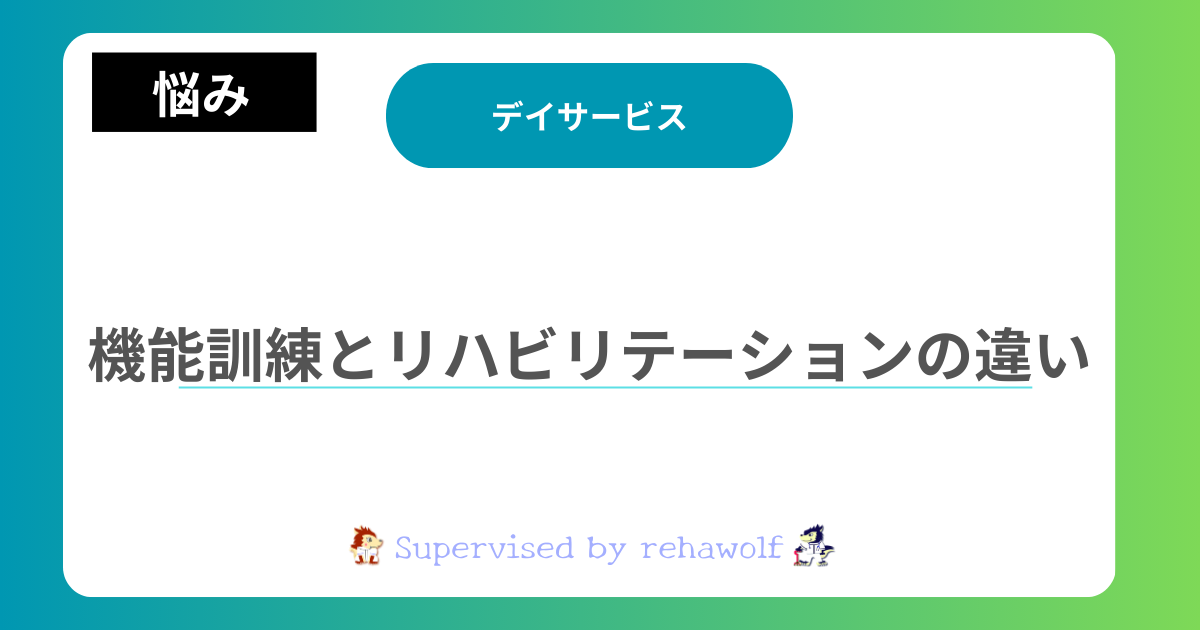
介護や医療の現場でよく耳にする「機能訓練」と「リハビリテーション」
一見似た言葉ですが、その意味や位置づけには明確な違いがあります。
「デイサービスで提供されるのは機能訓練?リハビリテーション?」「両者の境界線はどこにあるの?」と疑問を持つ方も多いでしょう。
本記事では、機能訓練とリハビリテーションの違いを整理し、デイサービスで行われる支援について詳しく解説します。
目次
機能訓練とは?
定義
機能訓練とは、介護保険制度において「心身機能の維持・向上を目的とした訓練」を指します。
日常生活を自立して送るために必要な 筋力・関節可動域・バランス・日常生活動作(ADL) などを改善・維持することが中心です。
実際の内容例
- 椅子に座って足を上げる運動
- 立ち上がりや歩行練習
- ストレッチや関節可動域訓練
- 箸やボタン掛けの練習
担当者
- デイサービスなど介護施設においては、機能訓練指導員(看護師・理学療法士・作業療法士など) が行います。
- 医師の指示に基づく医療行為ではなく、介護保険の範囲での支援です。
リハビリテーションとは?
定義
リハビリテーションは、医療の分野で広く使われる言葉で、単なる機能回復訓練だけでなく 「人間としての尊厳を持って社会生活に復帰すること」 を目的とした包括的な支援を意味します。
世界保健機関(WHO)はリハビリテーションを、
「障害を持つ人々が、可能な限り身体的・精神的・社会的に最良の状態を達成し、維持するためのあらゆる活動」
と定義しています。
実際の内容例
- 医師の診察・指示に基づく理学療法、作業療法、言語療法
- 外来リハビリや入院リハビリでの専門的訓練
- 医療的管理を伴うリハビリ(例:脳梗塞後の回復期リハ)
担当者
- 医師の指示のもと、理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST) が実施。
- 医療保険の対象となる。
機能訓練とリハビリテーションの違いを表で整理
| 項目 | 機能訓練 | リハビリテーション |
|---|---|---|
| 主な制度 | 介護保険 | 医療保険 |
| 目的 | 心身機能の維持・改善 | 社会復帰・生活全体の再建 |
| 実施場所 | デイサービス、特養、介護施設 | 病院、クリニック、回復期リハ病棟 |
| 担当職種 | 機能訓練指導員(看護師、PT、OTなど) | 医師、PT、OT、ST |
| 内容 | 筋トレ、歩行練習、ADL訓練 | 医学的リハ、社会参加支援、包括的アプローチ |
| 保険適用 | 介護保険サービス費+自己負担1〜3割 | 医療保険による診療報酬 |
デイサービスで行われるのはどっち?
デイサービスでは 「機能訓練」 が提供されます。
- 利用者の状態をアセスメント
- 個別機能訓練計画書を作成
- 集団体操や個別訓練を実施
ただし、理学療法士や作業療法士が配置されている事業所では、専門性の高いプログラムが受けられることもあり、リハビリに近い内容が含まれる場合もあります。
両者の共通点と補完関係
- 共通点:どちらも利用者の生活の質(QOL)を高めることを目的としている。
- 違い:医療保険か介護保険か、目的が「社会復帰」か「生活維持」かという点。
- 補完関係:医療機関でリハビリを受け、その後デイサービスで機能訓練を継続することで、生活全体を支える流れが多い。
まとめ
- 機能訓練:介護保険サービス。生活機能の維持・向上を目的に、デイサービスや介護施設で提供される。
- リハビリテーション:医療保険サービス。社会復帰を目的とした包括的な支援で、病院や専門機関で行われる。
- デイサービスでは「機能訓練」が中心だが、リハビリ専門職が関わることで医療的リハビリに近い支援を受けられることもある。
両者の違いを理解することで、介護保険と医療保険を上手に使い分けながら、利用者に合った支援を選ぶことができます。