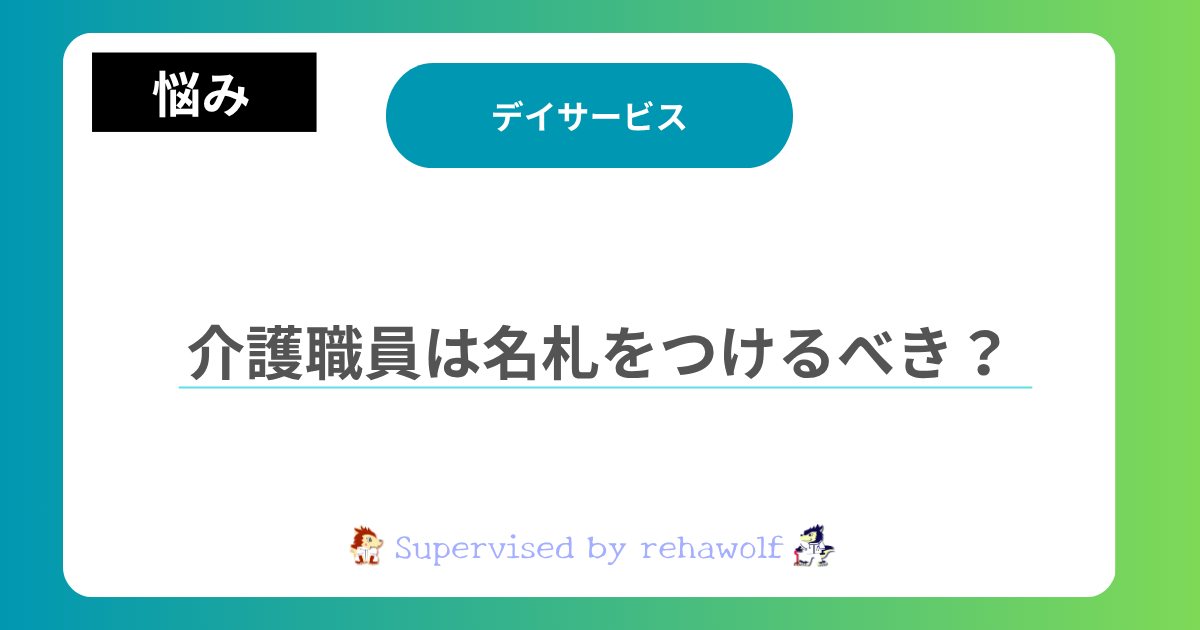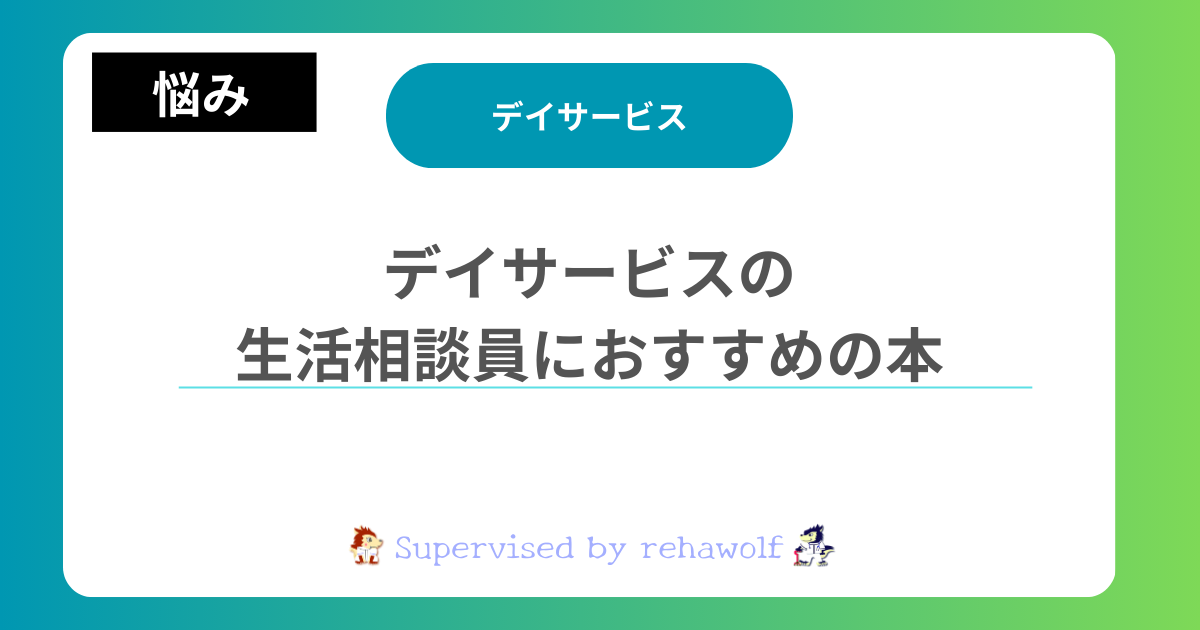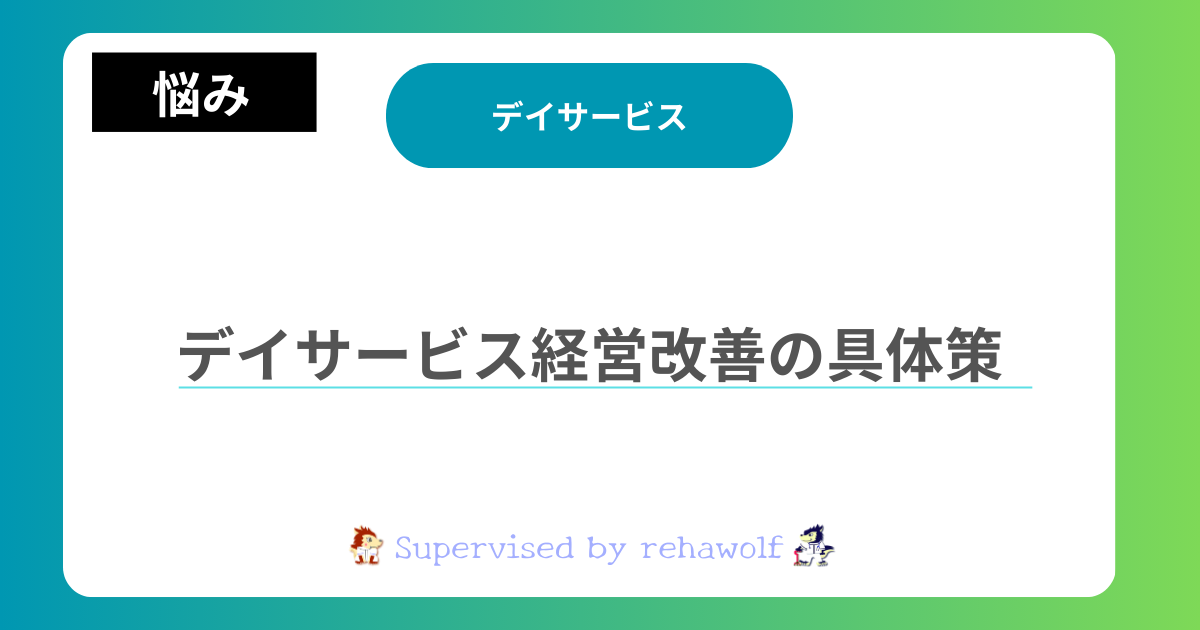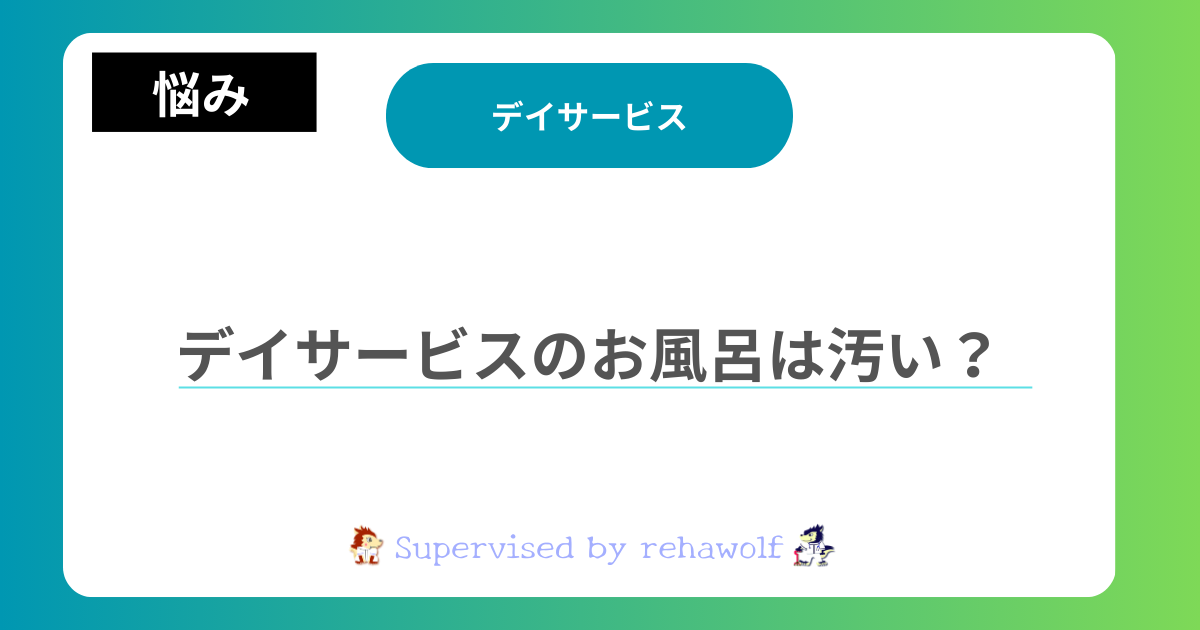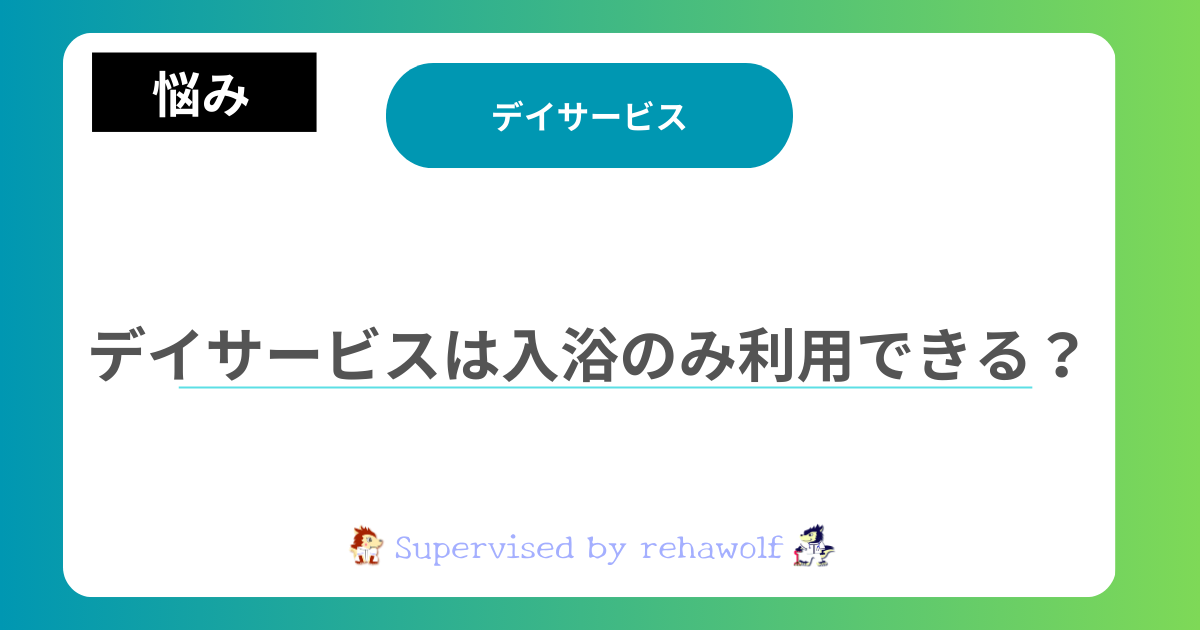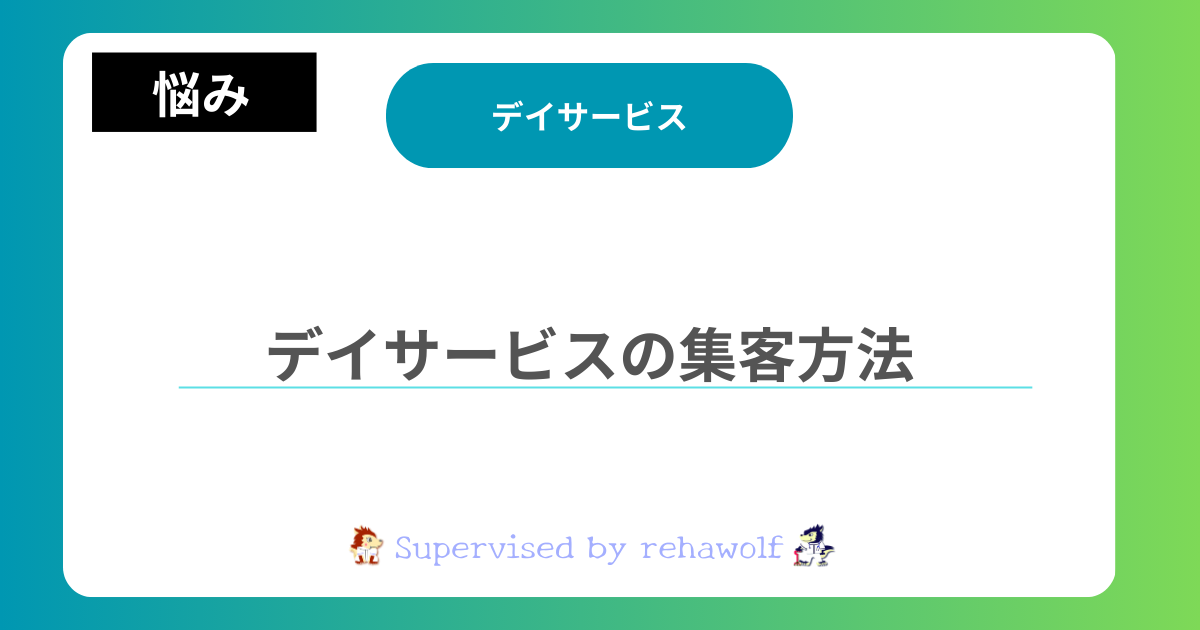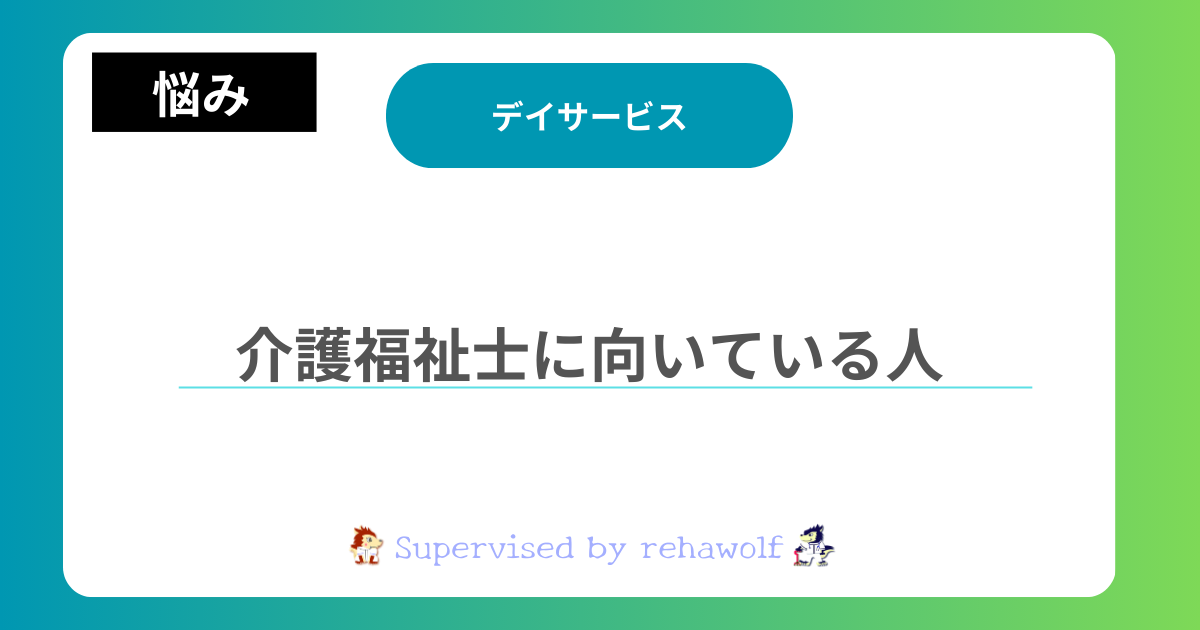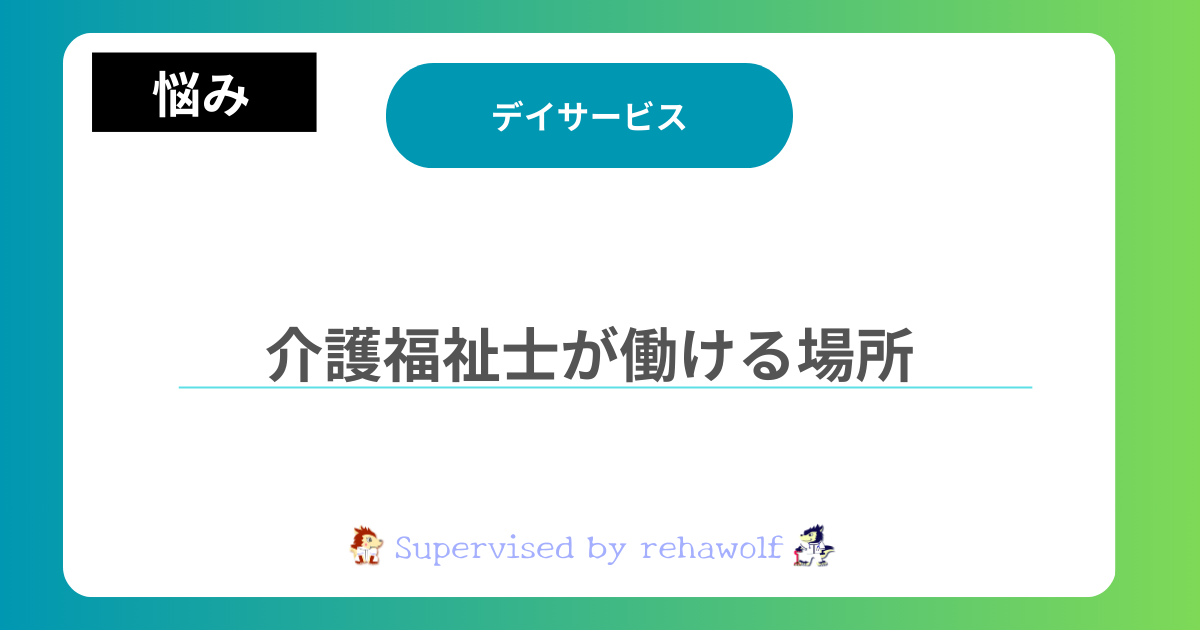【最新】通所介護(デイサービス)のおすすめの本を紹介
放課後等デイサービスの個別支援計画書とは?書き方と記入例をわかりやすく解説
当ページのリンクには広告が含まれています。
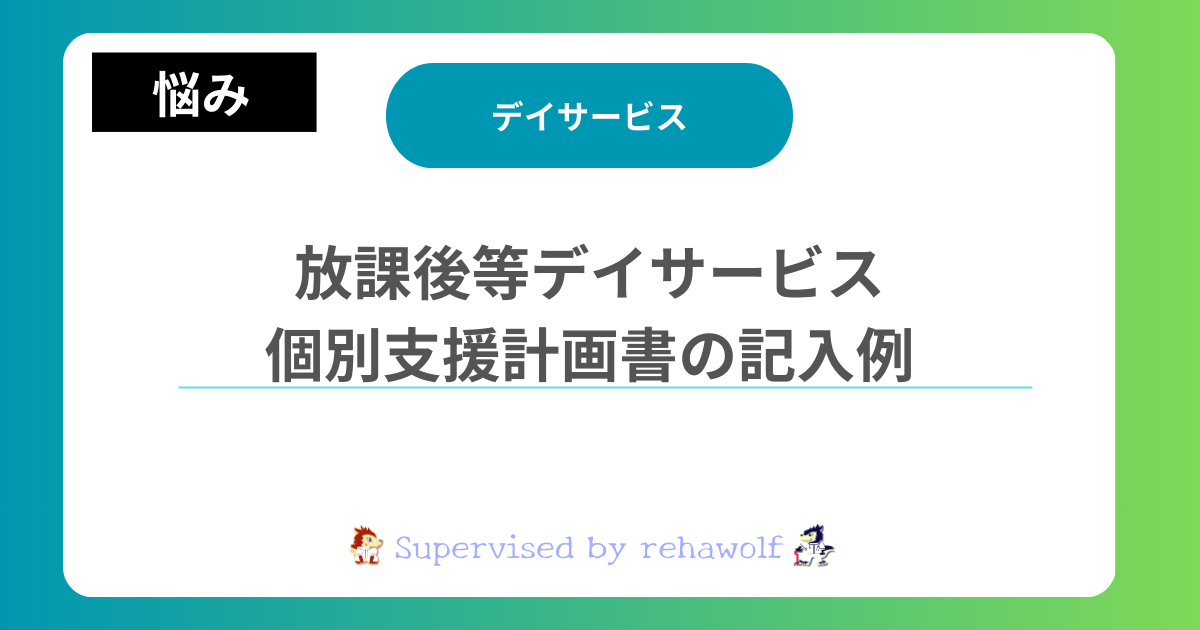
放課後等デイサービスを運営・利用するうえで欠かせないのが「個別支援計画書」です。
支援を必要とする子ども一人ひとりに合わせた計画を立てることで、適切な療育や発達支援につながります。
しかし、実際に作成する際には「どうやって書けばいいのか分からない」「記入例が欲しい」と悩む職員も少なくありません。
本記事では、放課後等デイサービスの個別支援計画書の概要や作成手順、具体的な記入例を紹介します。
目次
個別支援計画書とは?
個別支援計画書とは、子どもの障害特性や発達状況に応じて作成する支援の指針となる文書です。
児童発達支援管理責任者(児発管)が中心となり、保護者やスタッフと協力して作成します。
- 子どもの現状や課題を整理
- 具体的な目標を設定
- 支援内容や方法を明記
- 定期的に評価・見直しを行う
これらを通じて、継続的で一貫性のある支援が可能になります。
個別支援計画書の作成手順
- アセスメント(情報収集)
本人・保護者への聞き取り、学校との情報共有、観察などを行う。 - 課題の整理
発達面・行動面・生活面で必要な支援を抽出。 - 長期目標・短期目標の設定
長期的なゴールと、それに向けて取り組む具体的な短期目標を明記。 - 支援方法の記載
療育活動、生活習慣訓練、社会性の練習などを具体的に記載。 - 評価・モニタリング
定期的に計画を見直し、必要に応じて修正。
個別支援計画書の記入例
事例1:ADHDの小学生
- 長期目標:集団活動の中で順番を待てるようになる
- 短期目標:週2回の集団遊びで、職員の声かけにより3分間着席できる
- 支援方法:SST(ソーシャルスキルトレーニング)、ルールの明示、視覚的支援カードを使用
事例2:ASD(自閉スペクトラム症)の中学生
- 長期目標:自分の気持ちを簡単な言葉で表現できるようになる
- 短期目標:1日1回、職員の質問に「はい」「いいえ」で答えることができる
- 支援方法:絵カードの活用、視覚的スケジュールの提示、安心できる個別スペースの活用
事例3:知的障害のある児童
- 長期目標:日常生活で基本的な身の回りのことを自分で行えるようになる
- 短期目標:食事の際、自分でスプーンを使って5口以上食べられる
- 支援方法:職員が手を添えて介助、段階的に自立を促す練習
記入時のポイント
- SMARTの原則(具体的・測定可能・達成可能・現実的・期限付き)で目標を設定する
- 子どもや保護者の意見を取り入れる
- 書類のためではなく「支援に活かすため」に作成する
- 評価は「できた・できない」ではなく「進歩の程度」を重視する
よくある失敗例
- 目標が抽象的すぎる(例:「落ち着いて過ごす」など)
- 支援方法が具体的でない(例:「支援する」だけでは不十分)
- 評価や見直しが形骸化している
まとめ
放課後等デイサービスにおける個別支援計画書は、子どもの成長を支えるための重要なツールです。
「現状把握 → 課題整理 → 目標設定 → 支援内容 → 評価」という流れを意識することで、実際の支援に活かせる計画になります。
記入例を参考にしながら、子ども一人ひとりに合わせた計画を立てることが、質の高い放課後等デイサービスの提供につながります。