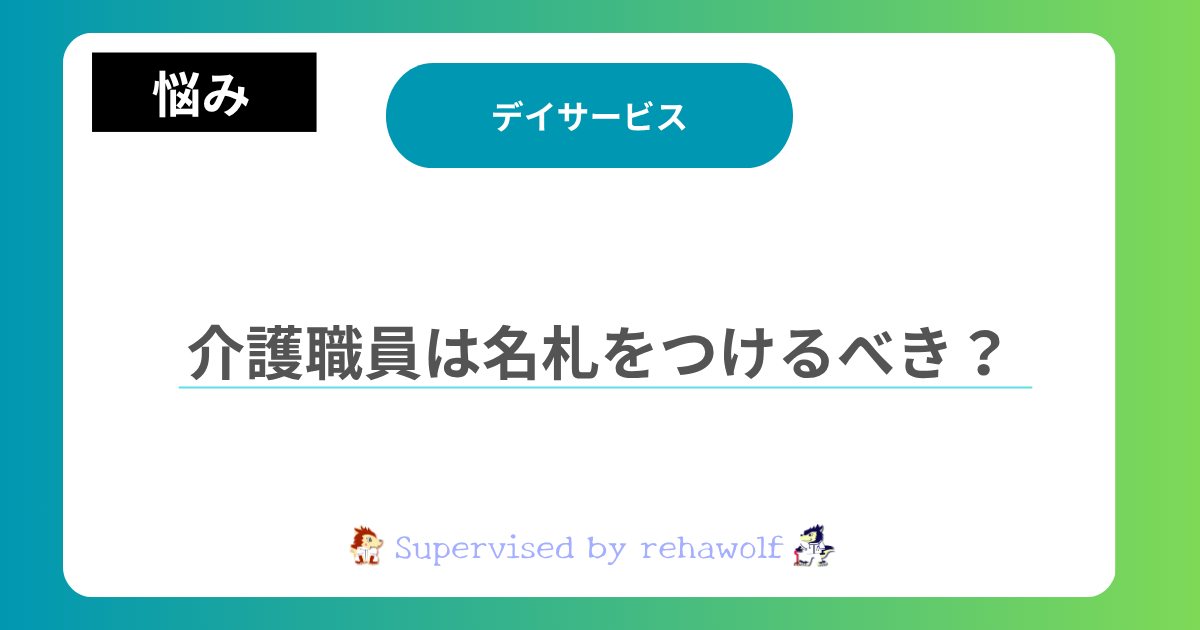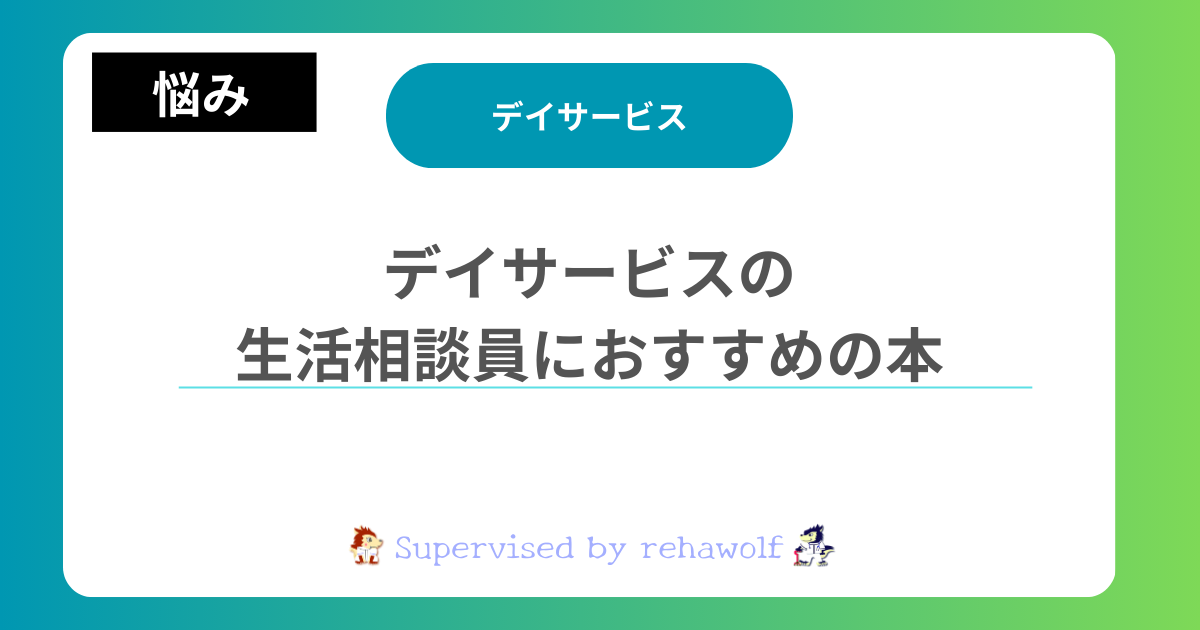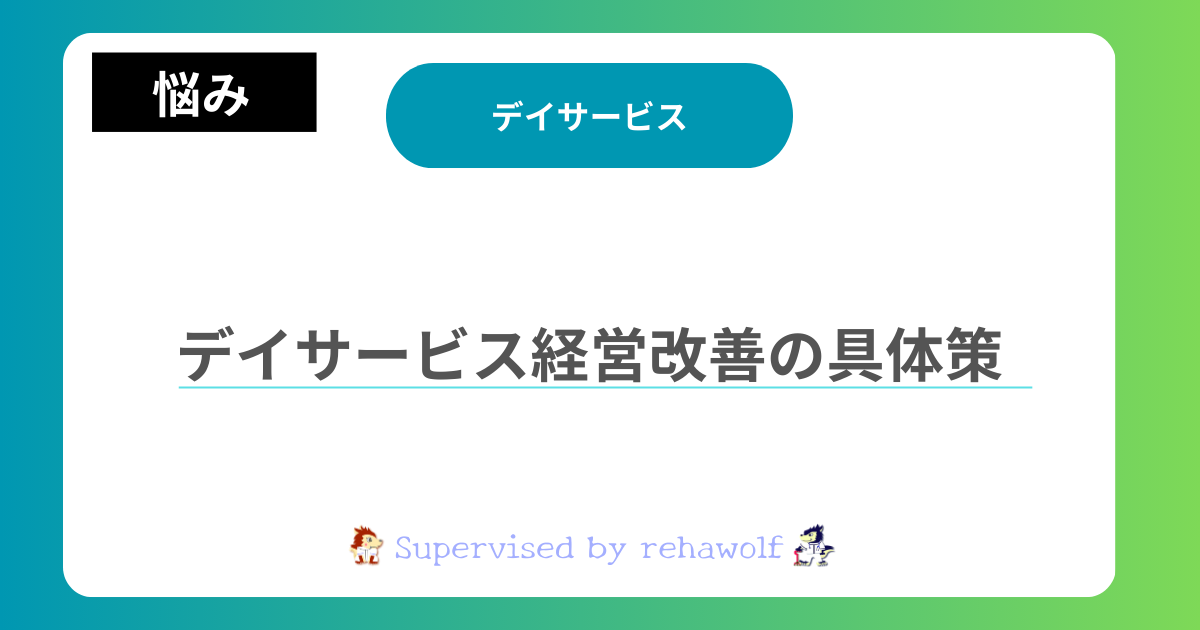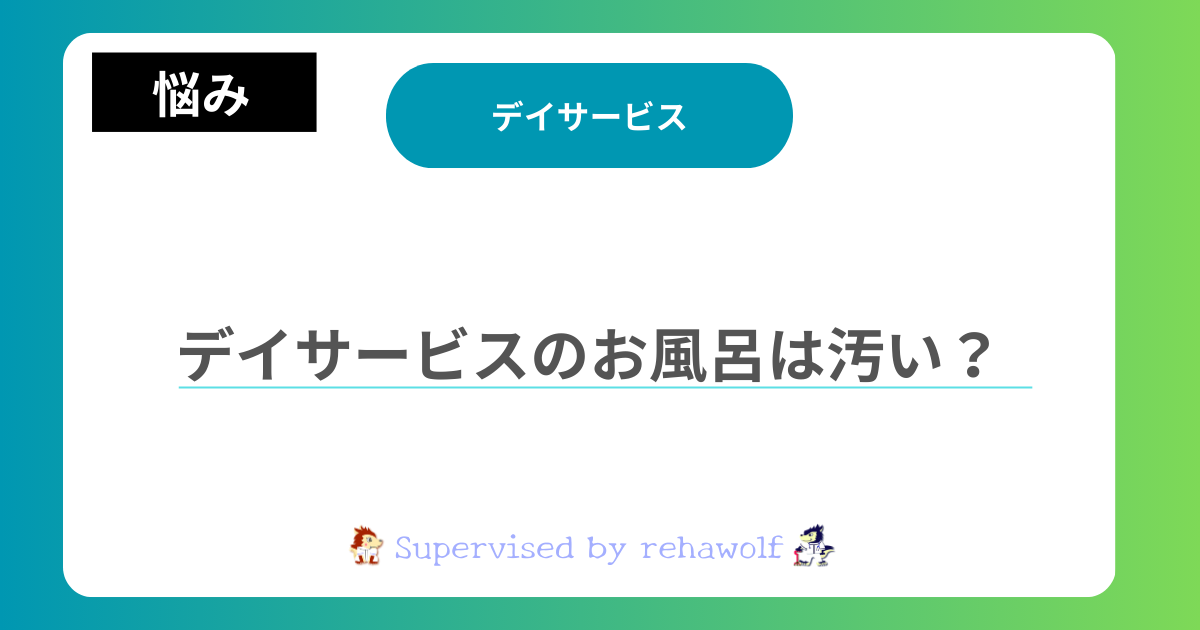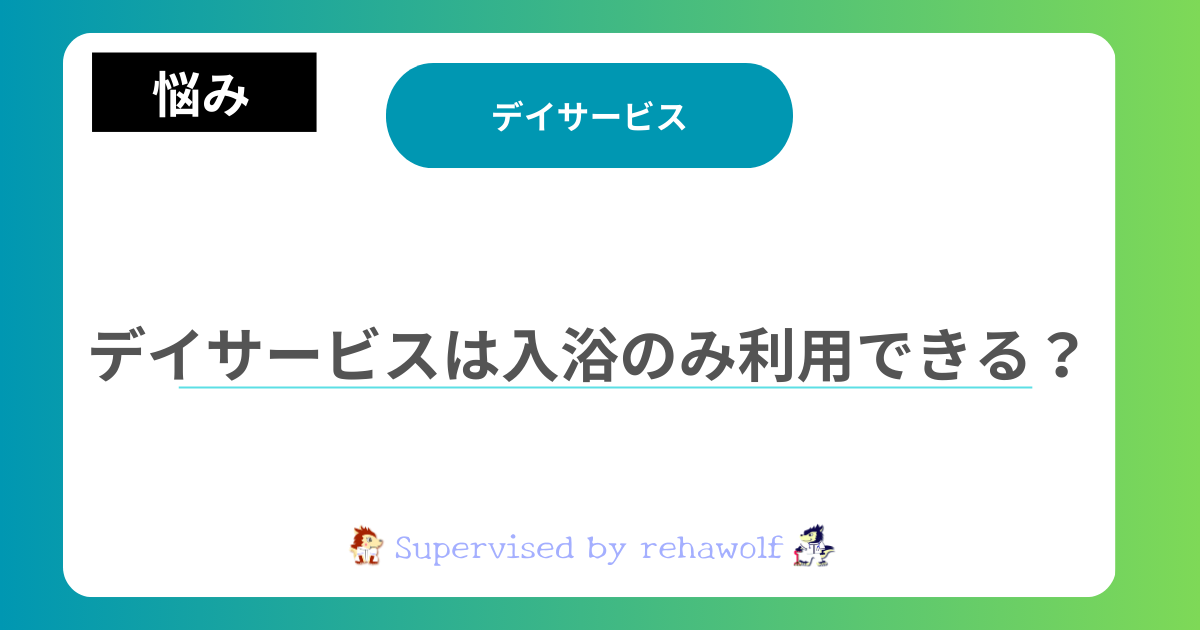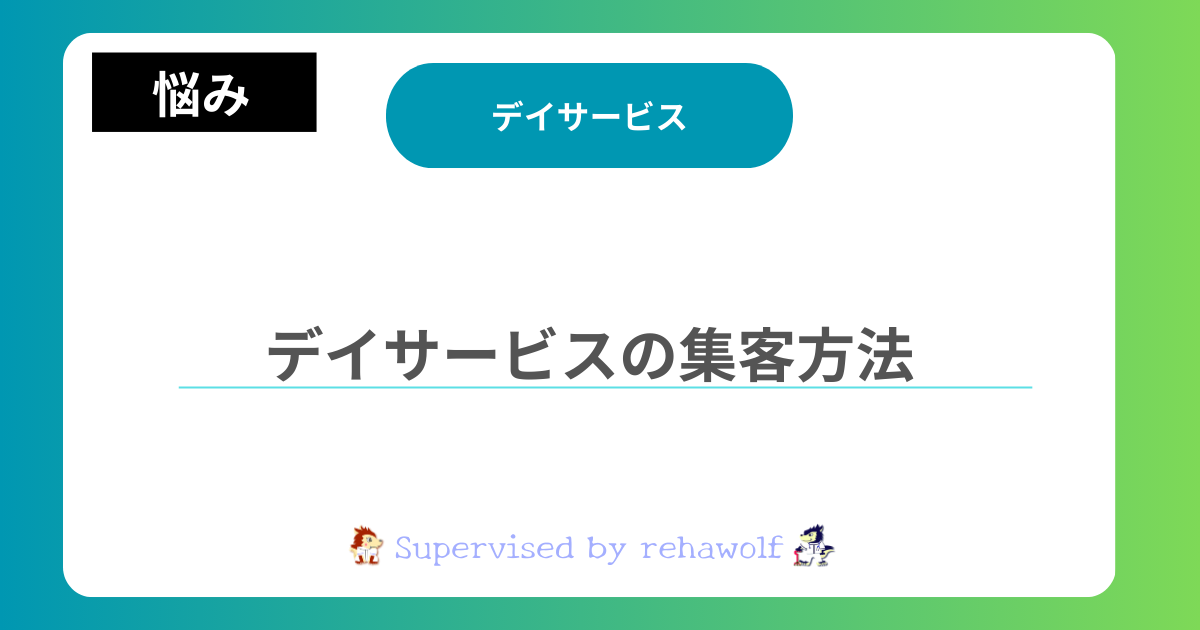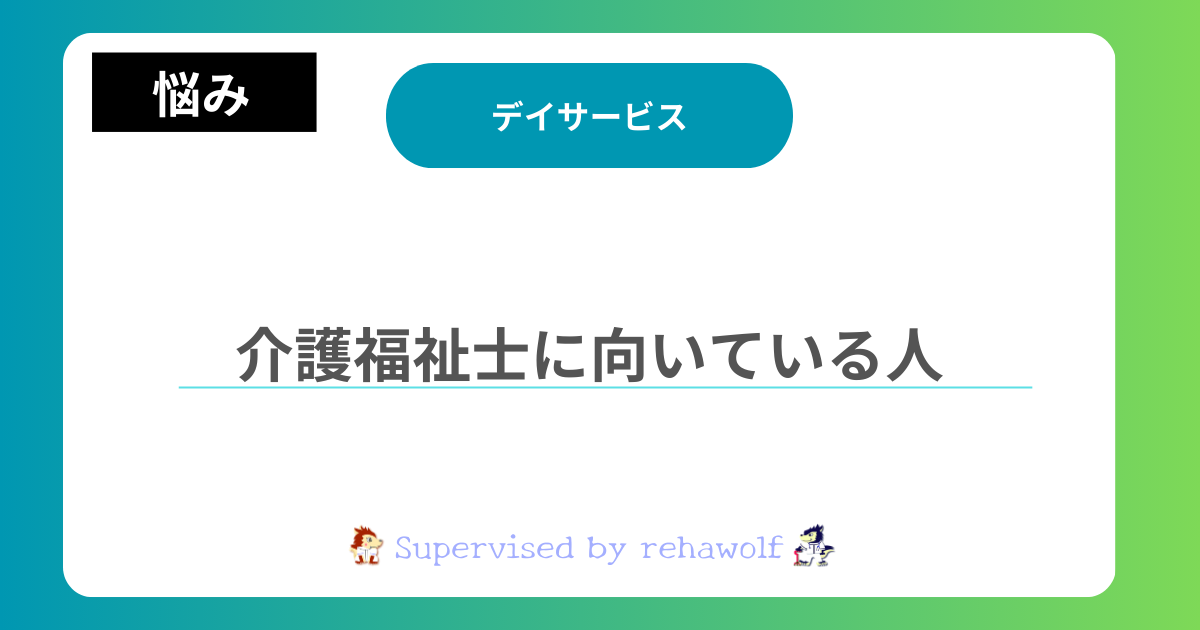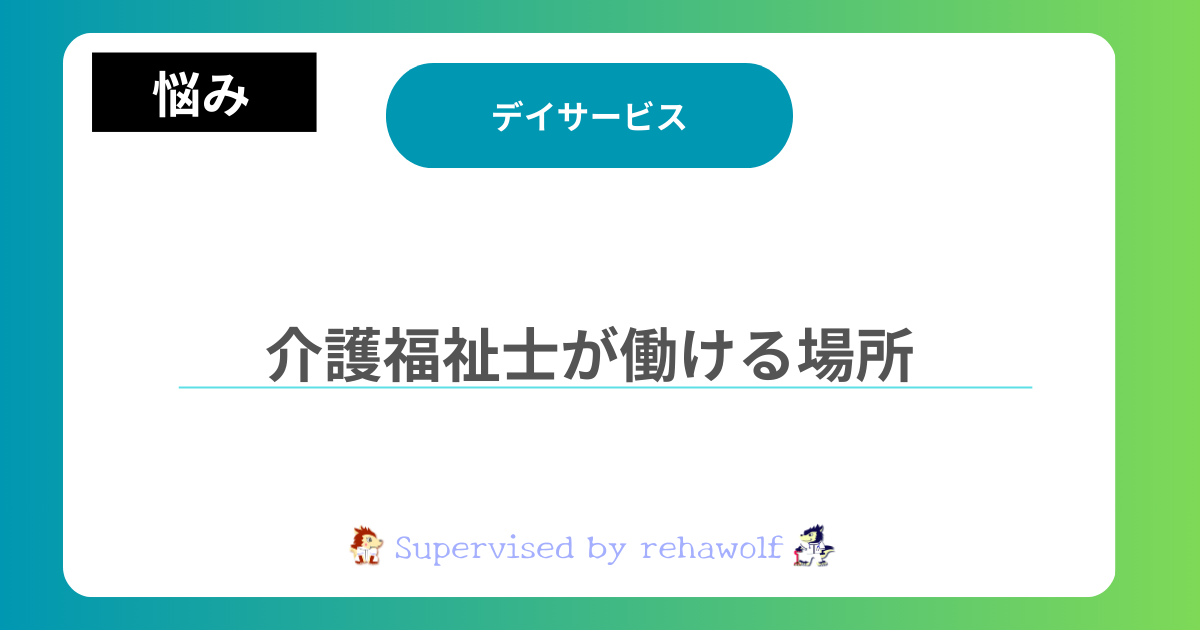【最新】通所介護(デイサービス)のおすすめの本を紹介
放課後等デイサービスにおける言語聴覚士(ST)の役割とは?子どもへの支援内容とメリットを解説
当ページのリンクには広告が含まれています。
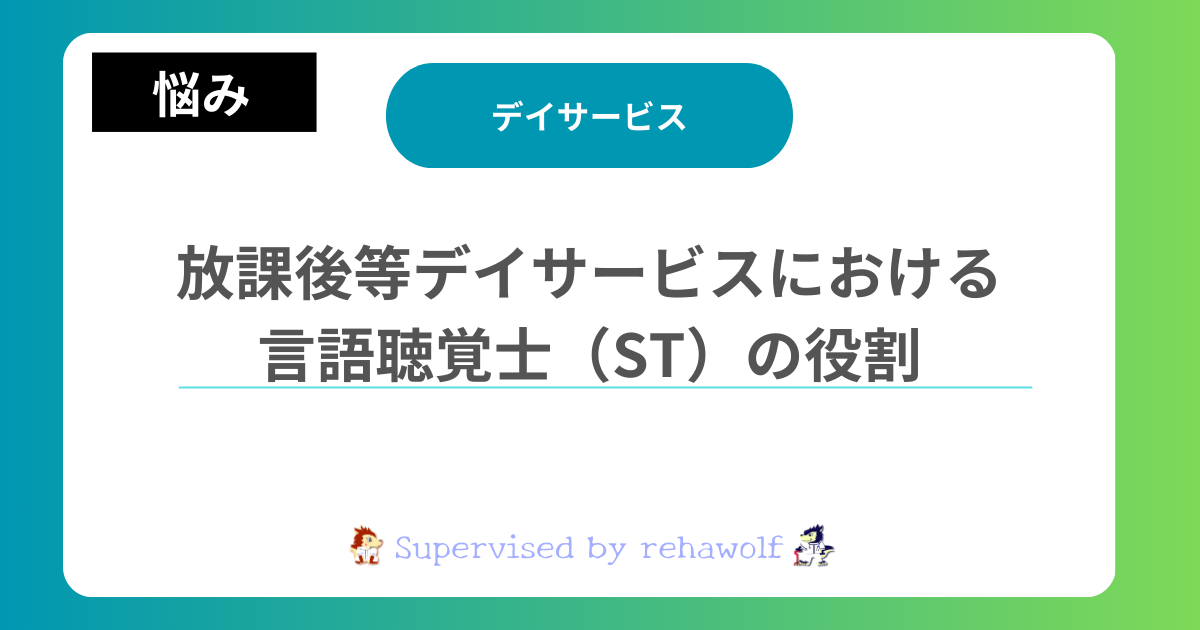
発達に課題を抱える子どもたちが放課後や長期休暇に利用できる 放課後等デイサービス(放デイ)。
その中で「ことばの遅れ」や「コミュニケーションの難しさ」「食べる・飲み込むの困難」に対応する専門職が 言語聴覚士(ST) です。
しかし「STがいる放デイといない放デイの違いは?」「どんな支援をしてくれるの?」と疑問に思う保護者も多いのではないでしょうか。
この記事では、放課後等デイサービスにおける言語聴覚士の役割やメリット、利用前に確認すべきポイントについて詳しく解説します。
目次
言語聴覚士(ST)とは?
言語聴覚士は国家資格を持つリハビリ専門職で、以下の領域を専門としています。
- ことばの発達支援(発音の練習、語彙力・理解力の向上)
- コミュニケーション支援(会話のやり取り、SST=ソーシャルスキルトレーニング)
- 摂食・嚥下支援(食べる・飲み込む動作の訓練)
- 学習支援(聴覚処理や記憶に関わるトレーニング)
特に発達障害や学習障害、構音障害のある子どもへの支援に強みを持ちます。
放課後等デイサービスにおける言語聴覚士の役割
1. ことばの発達支援
- 発音が不明瞭な子どもに対して構音練習
- 語彙を増やし、文章で話せるようにトレーニング
- 聞く力(聴理解)の向上サポート
2. コミュニケーション支援
- あいさつや会話の基本的なやりとりの練習
- 「順番を待つ」「人の話を聞く」などの社会的スキル指導
- AAC(コミュニケーションカード・タブレット)を使った代替手段の導入
3. 摂食・嚥下のサポート
- 食べにくさ、むせやすさがある子どもへの嚥下訓練
- 食事姿勢や食具の工夫の指導
- 保護者への食事支援アドバイス
4. 保護者・スタッフへの助言
- 家庭での声かけや遊び方の工夫を提案
- スタッフへの研修や支援方法のアドバイス
- 学校や医療機関との連携サポート
STが関わる放デイを利用するメリット
- ことばの発達に遅れがある子が 個別に指導を受けられる
- 食事や発音に関する不安を専門家に相談できる
- 医療と教育の橋渡し役 になり、療育の質が向上する
- 子どもの自信や自己表現力が高まり、学校生活にも良い影響を与える
注意点・留意点
- STは配置義務があるわけではないため、すべての放デイに在籍しているわけではない
- 常勤ではなく、非常勤や巡回(週に数回のみ)のケースも多い
- 利用を検討する際は 「STがいるか」「どのくらい関わってくれるか」 を必ず確認することが重要
利用前に確認すべきチェックポイント
- 言語聴覚士が在籍しているか(常勤 or 非常勤)
- STによる 個別支援計画 が作られているか
- 学校・医療機関と連携しているか
- 保護者へのフィードバックや家庭での練習指導があるか
まとめ
- 言語聴覚士(ST)は、ことば・コミュニケーション・嚥下の専門職。
- 放課後等デイサービスでは、発音練習や会話スキル、摂食訓練などを通して子どもの発達を支援する。
- STの配置は義務ではないため、利用前に「在籍の有無」「関わり方」を確認することが大切。
- STがいる放デイは、子どもの成長や家族の安心に大きなメリットをもたらす。