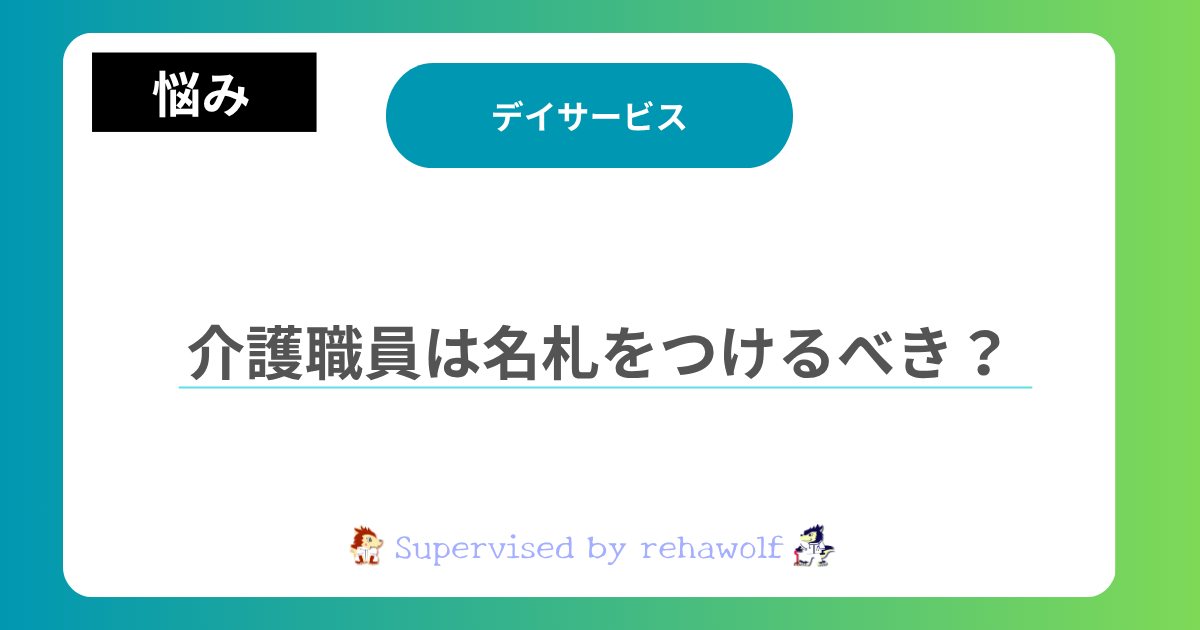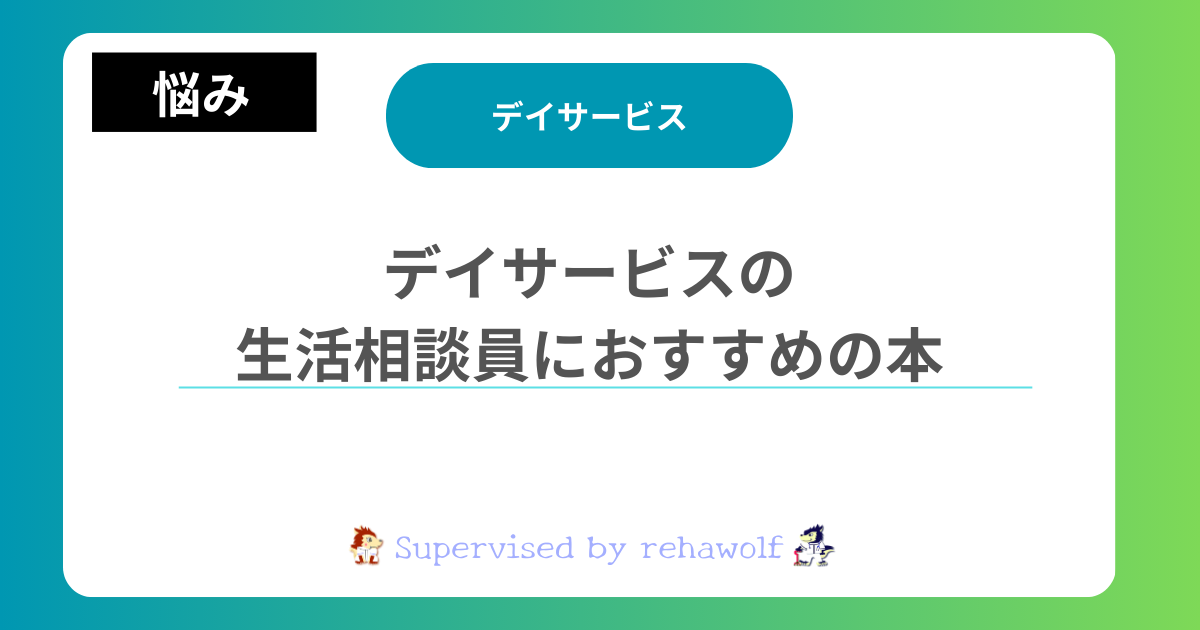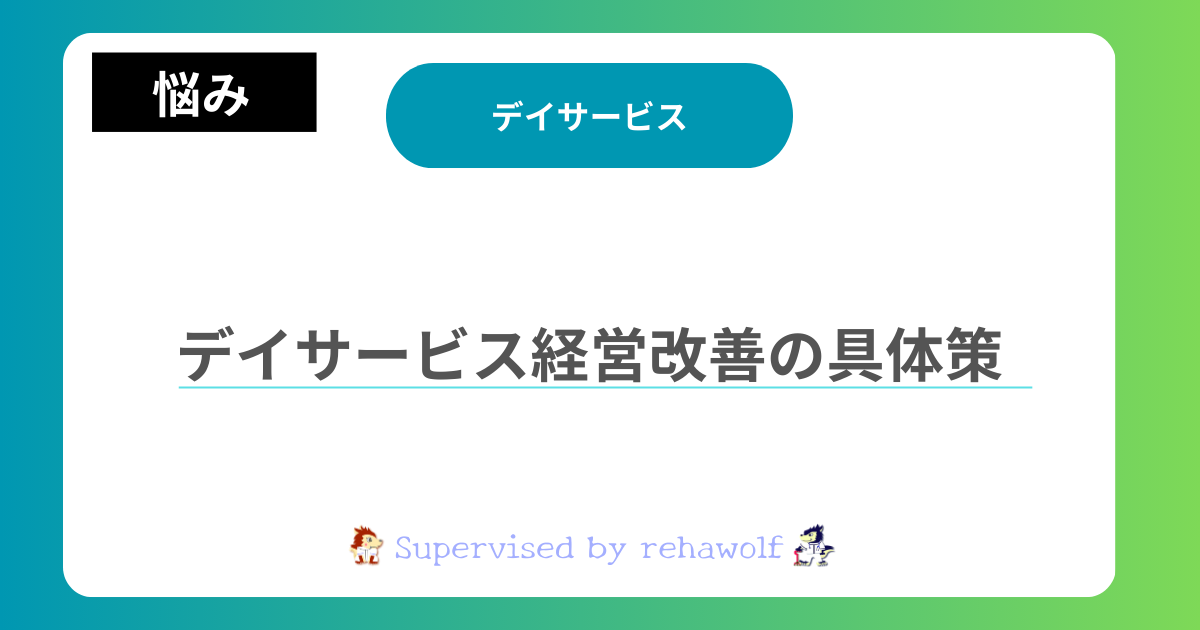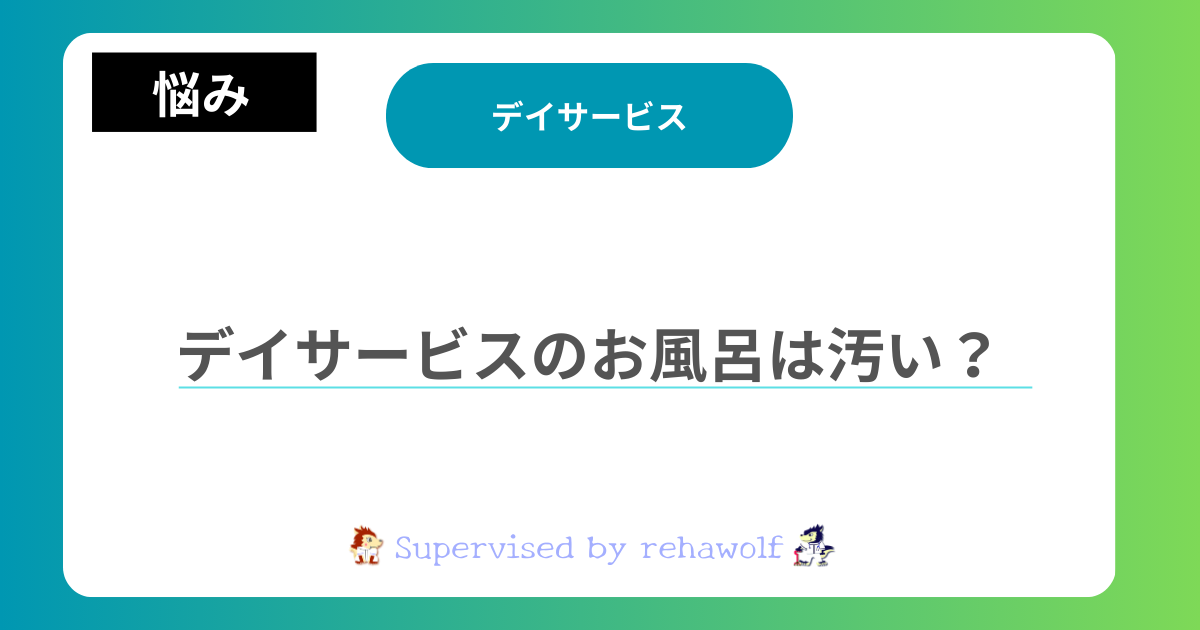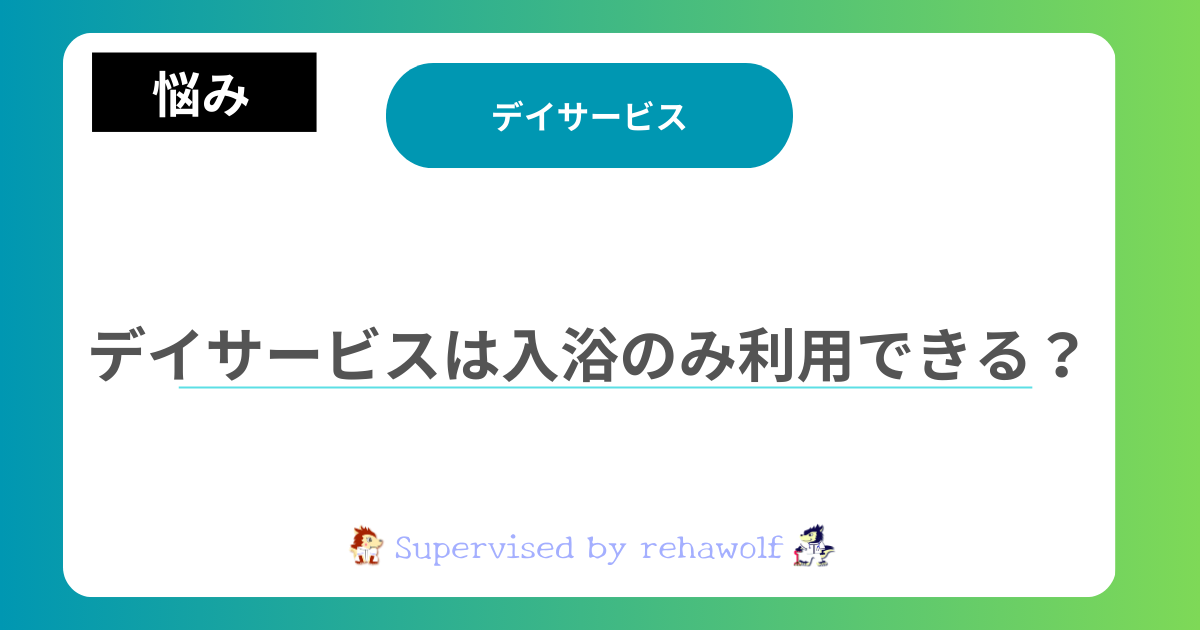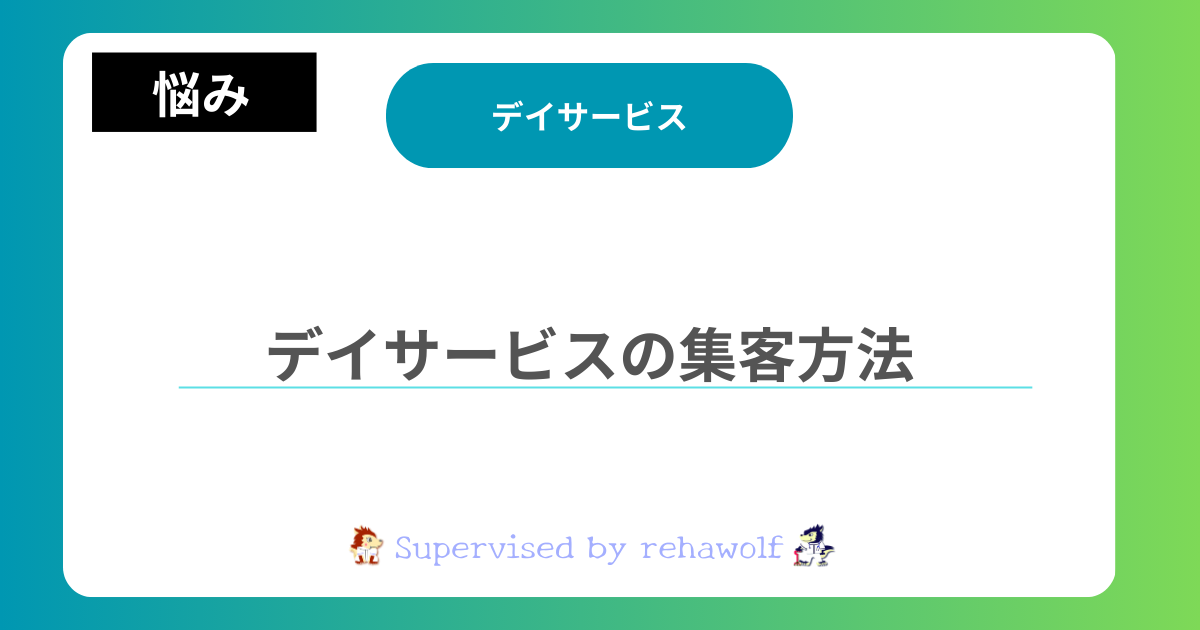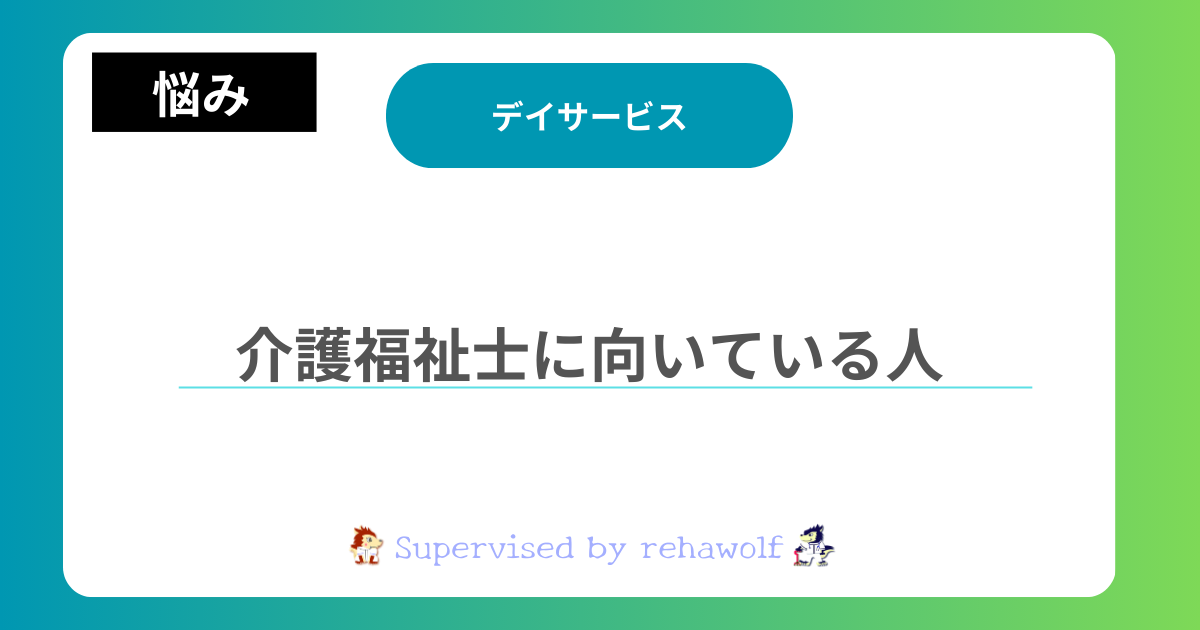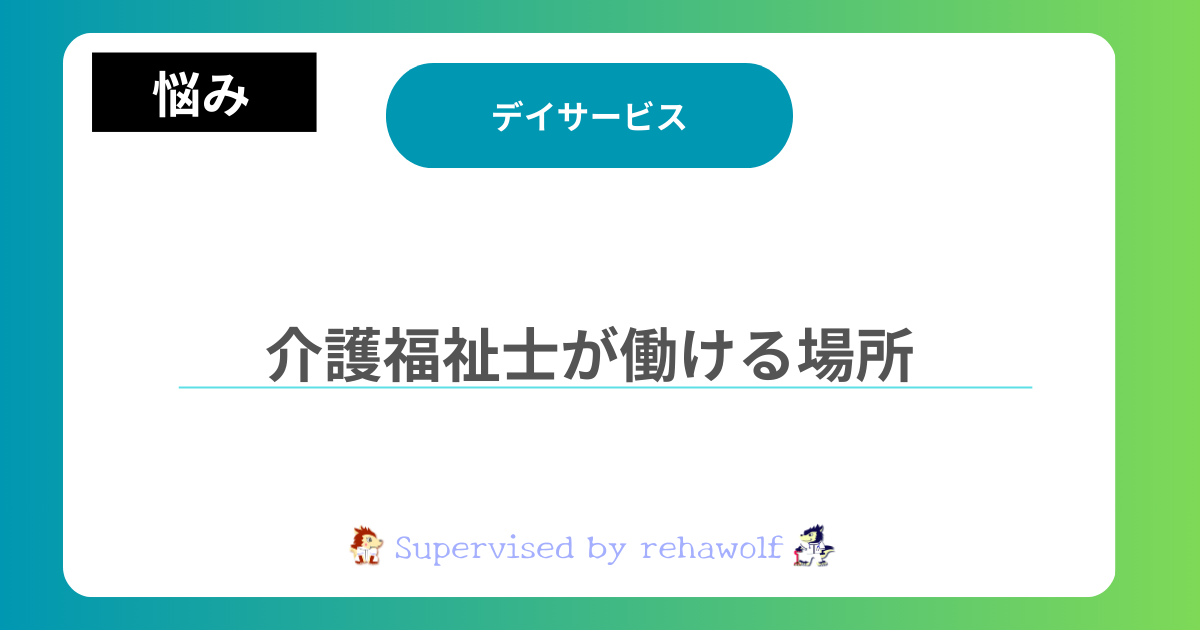【最新】通所介護(デイサービス)のおすすめの本を紹介
放課後等デイサービスの安全計画とは?作成方法と実践のポイントを解説
当ページのリンクには広告が含まれています。
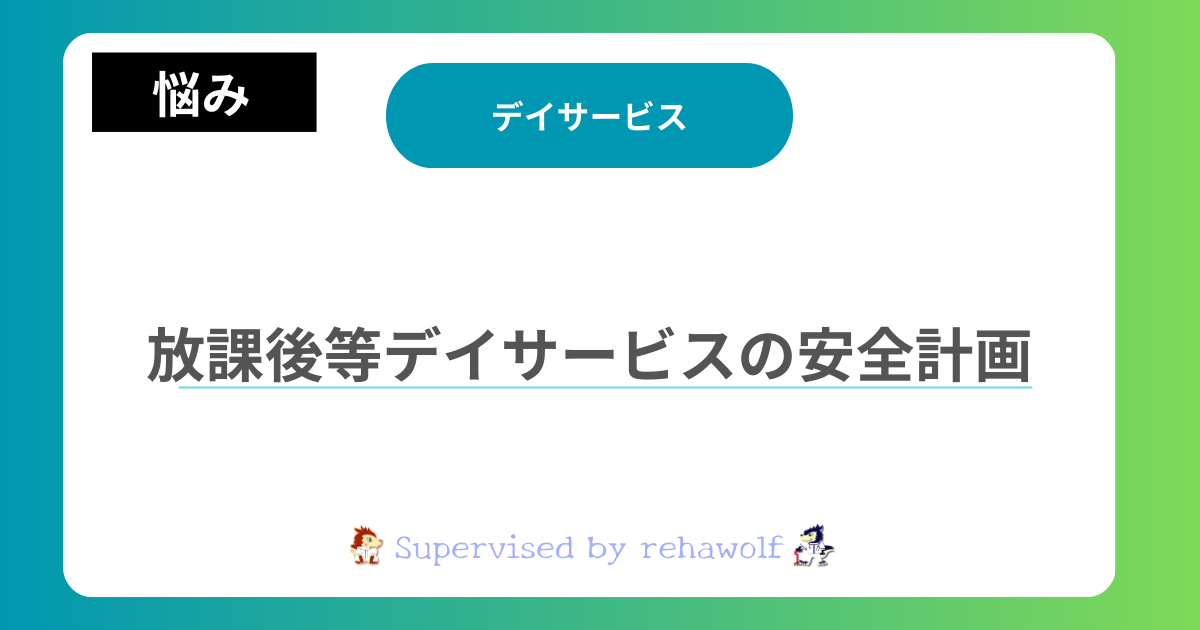
放課後等デイサービスを運営するにあたり、子どもたちの安心・安全を守るために欠かせないのが「安全計画」です。
安全計画は、施設内での事故防止や災害時の対応、送迎中の安全確保などを定めたもので、事業所に義務付けられています。
本記事では、放課後等デイサービスにおける安全計画の概要、具体的な内容例、作成の流れ、そして実際に運用する際の注意点について詳しく解説します。
目次
放課後等デイサービスにおける安全計画とは?
安全計画とは、事業所で発生し得る事故や災害などのリスクに備え、未然に防ぐための取り組みや、発生時の対応をまとめたものです。
厚生労働省のガイドラインでも、放課後等デイサービスや児童発達支援において「安全確保のための計画策定・実施」が求められています。
- 子どもの命を守るための事前準備
- 職員が統一した行動を取るための指針
- 保護者へ安心を提供するための重要なツール
安全計画に盛り込むべき内容
1. 事故防止対策
- 室内の転倒・転落防止策
- 誤飲・誤嚥を防ぐ工夫
- 入浴や水遊び活動時の監視体制
2. 災害時の対応
- 地震・火災・水害などの災害別避難マニュアル
- 避難経路や避難場所の確認
- 定期的な避難訓練の実施
3. 送迎時の安全
- 車両点検や運転者の安全教育
- シートベルト・チャイルドシートの徹底
- 乗降時の事故防止(職員が必ず確認)
4. 感染症対策
- 手洗い・うがい・消毒の徹底
- 発熱や体調不良児への対応手順
- 流行期における活動内容の調整
5. ヒヤリ・ハット報告体制
- 小さな事故やヒヤリとした出来事を記録・共有
- 職員間での再発防止ミーティング
- 保護者への適切な報告
安全計画の作成手順
- リスクの洗い出し
活動内容や施設環境から起こりうるリスクをリスト化。 - 対応策の検討
発生確率や重大性を踏まえて優先度を決め、対策をまとめる。 - 計画書の作成
活動ごとの安全対策や緊急時対応を文書化。 - 職員への周知・研修
全職員が理解し、実際に行動できるよう研修を行う。 - 定期的な見直し
事故やヒヤリハットの事例をもとに計画を改善。
安全計画の具体例(抜粋)
- 活動中の安全管理
・運動遊びの際は職員2名以上で見守る
・はさみや針など危険物は施錠保管 - 災害時対応
・地震発生時は机の下に避難 → 揺れが収まったら屋外へ
・火災時は非常口から近隣の小学校へ避難 - 送迎時のルール
・車両点検表を毎日記録
・乗降時は職員が名前を呼んで点呼
安全計画を実効性のあるものにするポイント
定期的な訓練
避難訓練・送迎訓練は年に複数回実施し、子どもも職員も実際に動けるようにする。
保護者との連携
緊急時の連絡体制や引き渡し方法を共有しておく。
外部との協力
地域の消防署・警察・学校などと連携し、実効性のある体制を整える。
まとめ
放課後等デイサービスの安全計画は、子どもたちの命を守り、安心して過ごせる環境を提供するための必須事項です。
- 事故防止・災害対応・送迎安全・感染症対策を明記
- 職員全員が理解し実行できる仕組みづくり
- 定期的な見直しと改善が重要
計画を「書類のため」に終わらせず、現場で活用できる内容にすることが、質の高い放課後等デイサービス運営につながります。