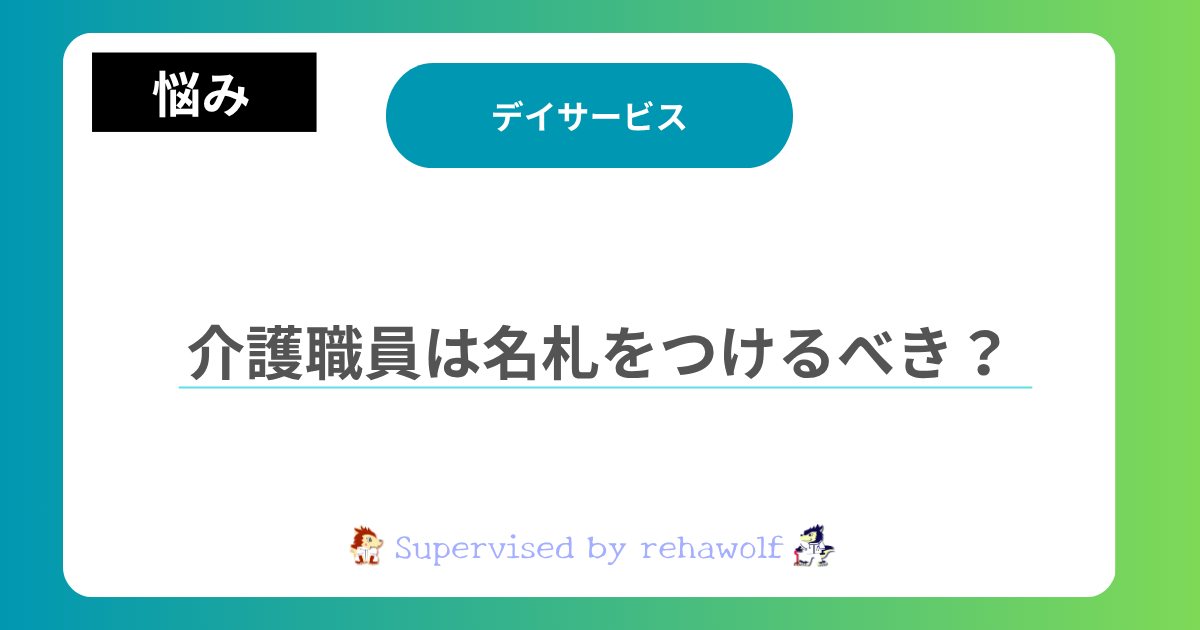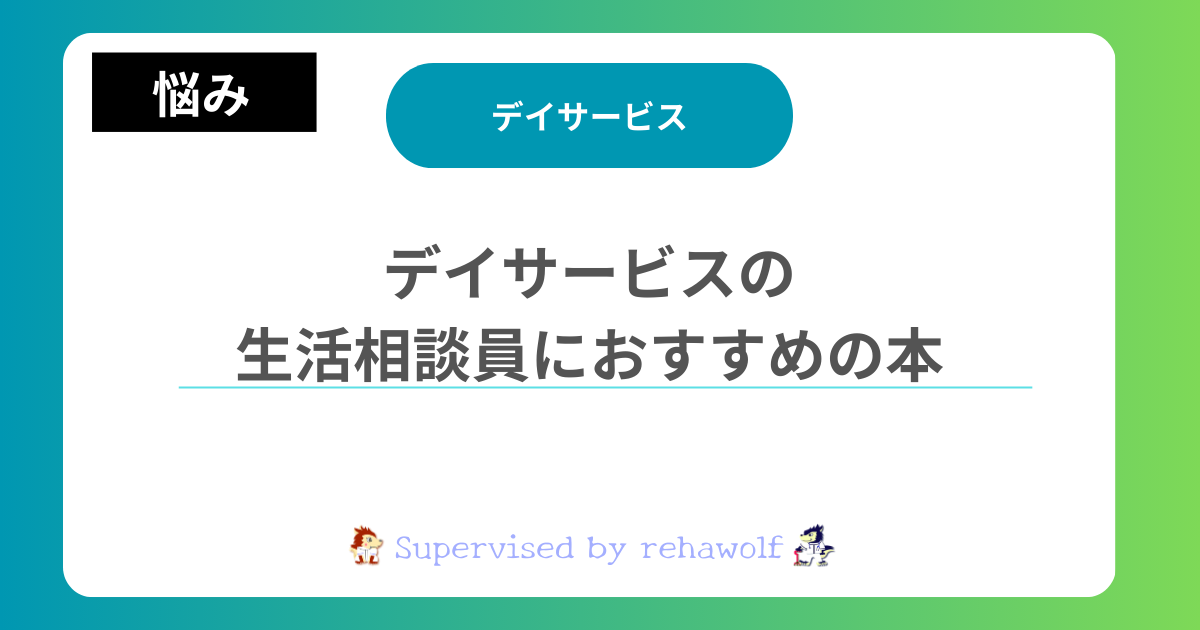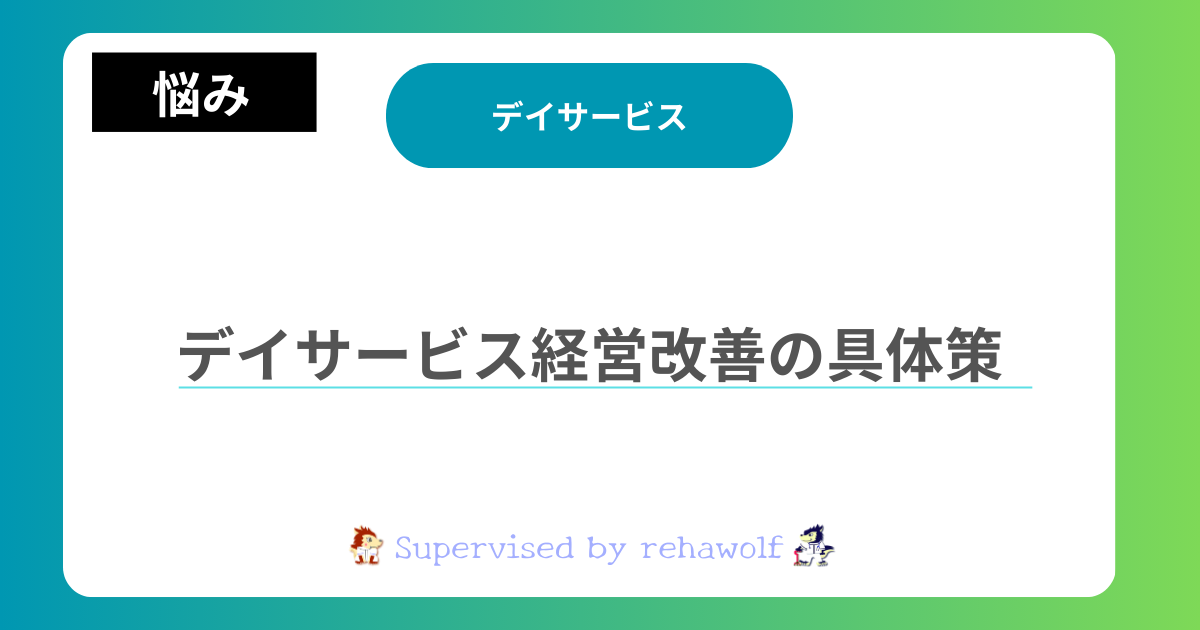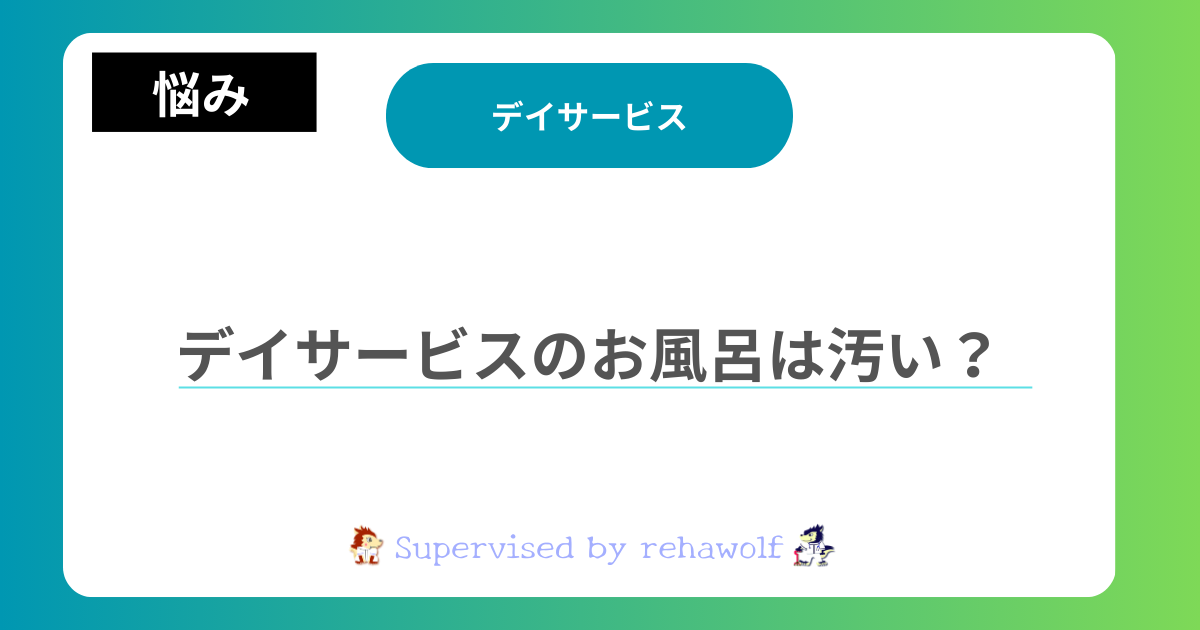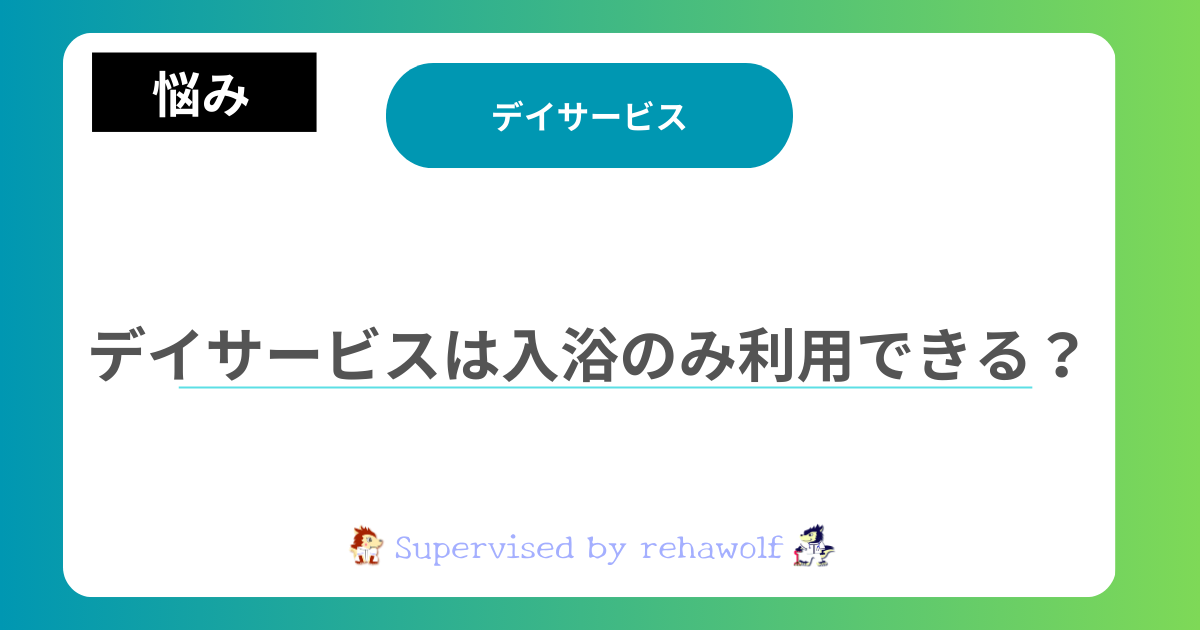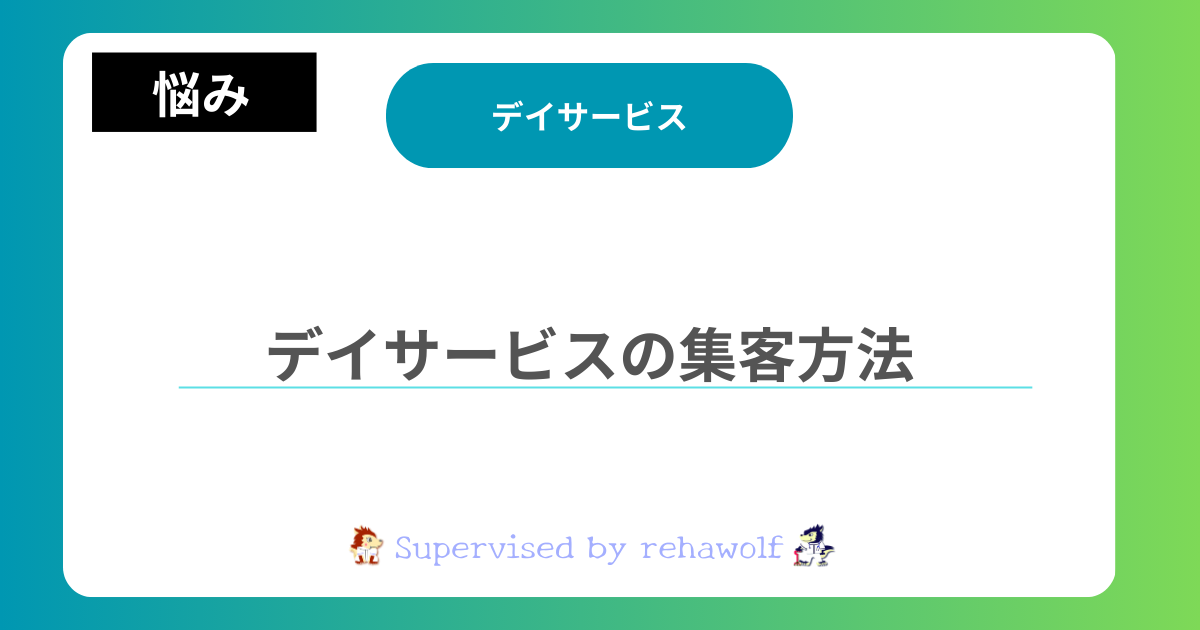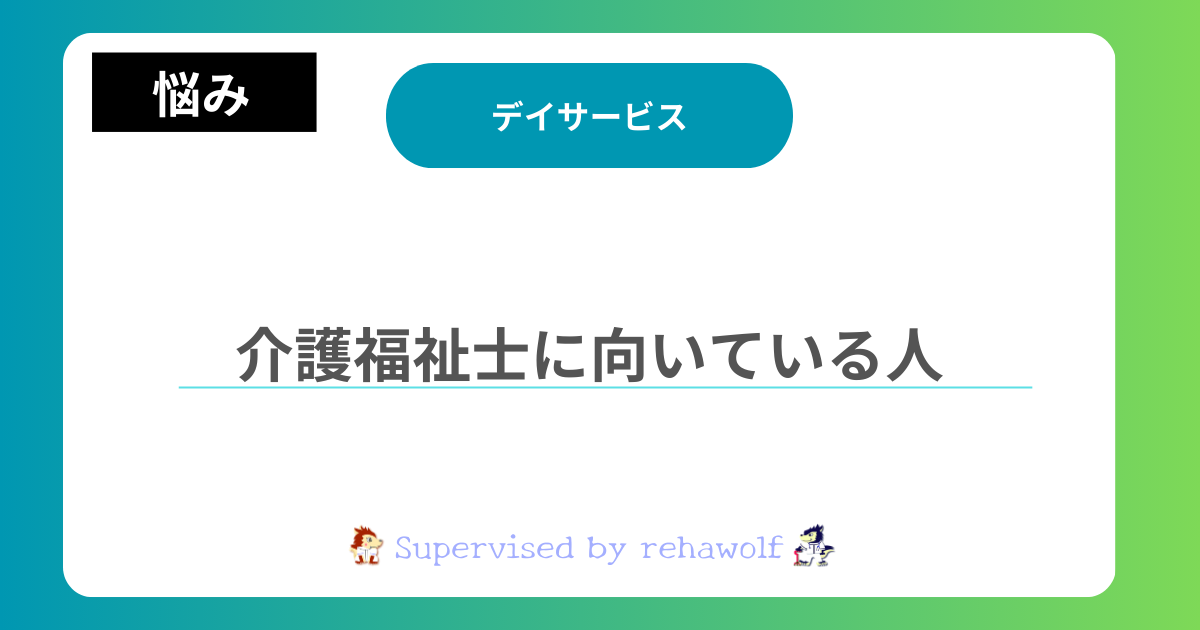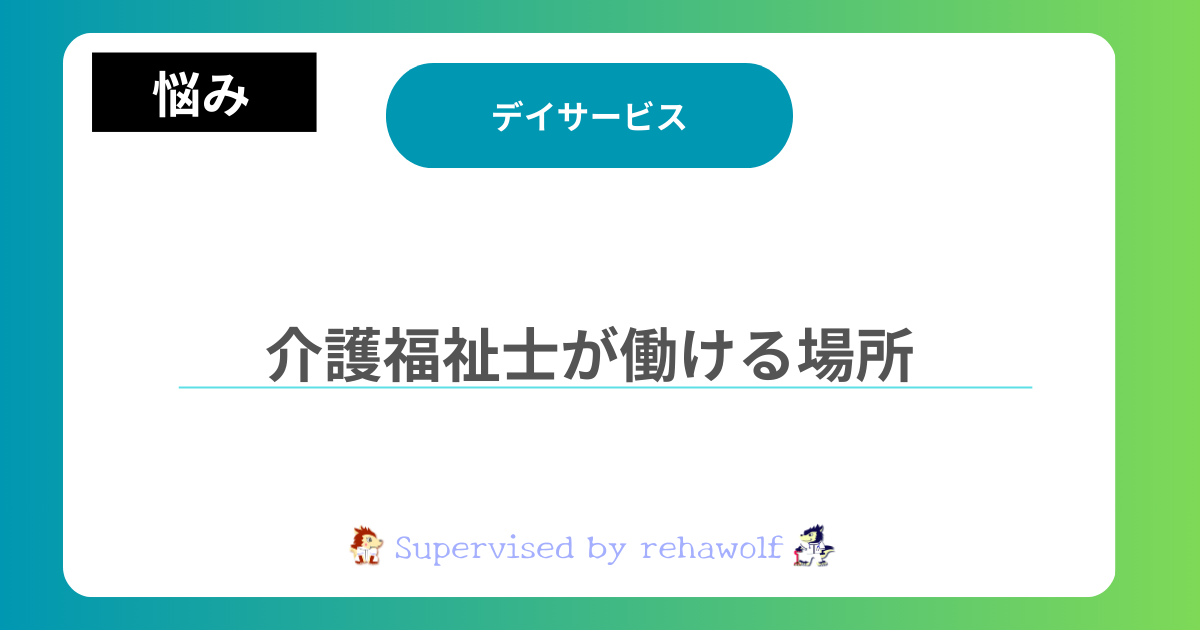【最新】通所介護(デイサービス)のおすすめの本を紹介
高齢者向け輪投げのルールを徹底解説!簡単で楽しいレクリエーションに活用しよう
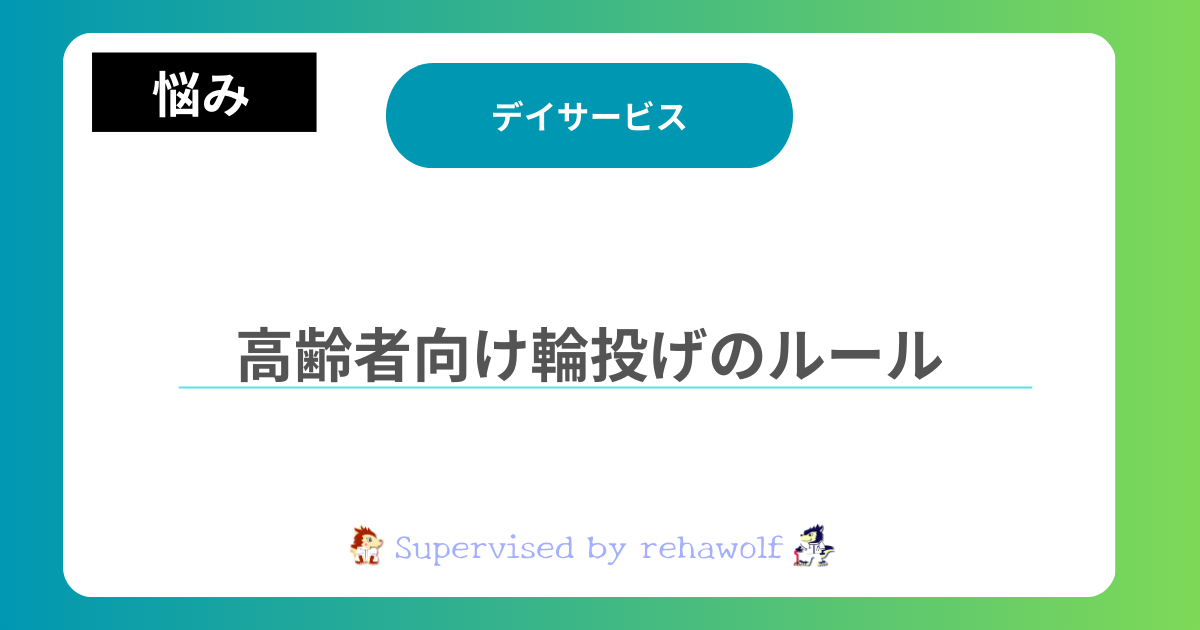
デイサービスや介護施設で人気のレクリエーションのひとつに「輪投げ」があります。
輪を的に投げて得点を競うシンプルなゲームですが、年齢や身体機能に関係なく誰でも楽しめることから、高齢者の心身機能の維持・向上や交流の場として広く取り入れられています。
本記事では、高齢者向け輪投げの基本的なルール、施設で実際に行われているアレンジ方法、そしてリハビリや認知症予防につながる効果について詳しく解説します。
輪投げの基本ルールとは?
使用する道具
- 輪:プラスチックや布製で直径15〜20cm程度のものが一般的
- 的(台):数字が書かれた棒を立てた台。1〜9までの番号がついていることが多い
基本的な遊び方
- 利用者は決められた距離から輪を投げる
- 的の棒に輪が入ったら、その番号が得点になる
- 輪の本数は5本〜10本程度が一般的
- 合計点を計算して勝敗を決める
投げる距離
高齢者の場合、2〜3m程度の距離に設定するのが目安です。身体機能や車椅子利用の有無によって距離を調整します。
高齢者向けにアレンジされたルール例
① 時間制ルール
制限時間(例:1分以内)で何本輪を入れられるかを競います。集中力や瞬発力を養う効果があります。
② チーム戦ルール
個人戦ではなく、2〜3人のチームで合計得点を競います。協力し合うことで交流が深まり、コミュニケーションの活性化にもつながります。
③ 難易度調整ルール
- 的の数字に点数をつけ、中央は高得点、外側は低得点にする
- 輪の大きさや投げる距離を変えてハンデをつける
④ ビンゴ方式
数字が書かれた台に輪を入れ、縦・横・斜めのラインが揃ったら勝ち。ゲーム性が高まり盛り上がります。
輪投げで得られる効果
身体機能の向上
- 腕の可動域を広げ、肩や肘の運動になる
- 立位で行えばバランス能力や下肢筋力の維持につながる
- 車椅子利用者でも上半身運動として効果的
認知機能の活性化
- 的の番号を狙うことで注意力や集中力が高まる
- 得点計算で計算力や記憶力を刺激する
- 勝敗を意識することで意欲が向上する
社会的効果
- ゲームを通じて会話が生まれる
- 仲間と応援し合うことで孤立感を防ぐ
- 成功体験を得ることで自信や達成感につながる
輪投げを安全に楽しむためのポイント
事故防止
- 投げる前に周囲の安全を確認する
- 的を安定した場所に設置する
- 足元が滑らないようにマットを敷く
難易度の調整
- 身体機能に合わせて距離や輪の大きさを変える
- 車椅子利用者は前方にスペースを確保する
- 認知症の方には「近くからでもOK」など柔軟にルールを調整
盛り上げ方
- 音楽や拍手で場を盛り上げる
- 得点表をホワイトボードに記録する
- 小さな景品を用意して意欲を高める
デイサービスでの輪投げ活用例
午後のレクリエーションとして
昼食後の時間帯に実施すると、眠気防止や活動量確保に効果的です。
機能訓練に組み込む
理学療法士や作業療法士が関与する場合、肩の可動域訓練や立位保持訓練として輪投げをアレンジすることもあります。
季節イベントに合わせて
夏祭りや運動会など、行事レクリエーションとして輪投げ大会を実施すると盛り上がります。
まとめ
高齢者向けの輪投げは、シンプルでわかりやすく、誰でも参加できる人気のレクリエーション です。基本ルールは「決められた距離から輪を投げ、番号の棒に入ったら得点」とシンプルですが、チーム戦やビンゴ方式などにアレンジすることで、さらに楽しく盛り上がります。
身体機能の維持・向上、認知機能の活性化、交流促進といった効果も期待でき、デイサービスや高齢者施設にとって取り入れやすい活動です。安全面に配慮しながら、利用者一人ひとりに合ったルール設定を工夫することで、楽しい時間を提供できるでしょう。